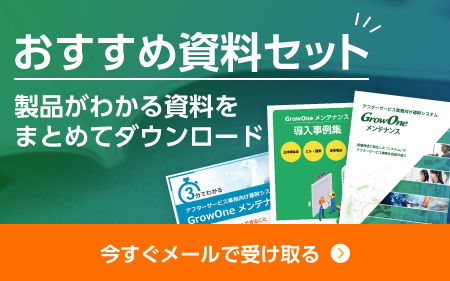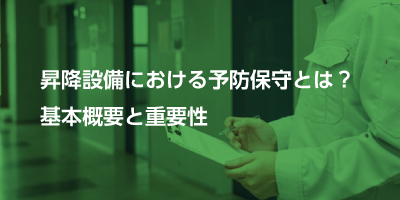保守メンテナンスシステムとは? 導入のメリットと徹底比較

2025年9月10日
保守メンテナンス業務を効率化し、現場作業のミスを減らすために、システム導入が注目されています。
本記事では、保守メンテナンスシステムの特徴や機能、導入事例などを紹介し、導入のメリットと注意点を整理します。合わせて、具体的なシステムの特徴や導入手順についても、わかりやすく解説します。
目次
1.2. 現場情報のリアルタイム共有の必要性
2.1. 作業効率向上と人的ミスの削減
2.2. データ連携と現場DXの実現
2.3. 顧客満足度向上につながるサービス強化 3.1. 設備・機器管理機能
3.2. 作業指示・スケジュール管理機能
3.3. 帳票・報告書管理機能
3.4. 顧客・契約管理機能
3.5. 外部システム連携やデータ分析 4.1. 基幹業務統合型(販売管理・在庫管理を含む)
4.2. アフターサービス対応管理特化型
4.3. 活動管理向けタイプ 5.1. 建物・設備保全での利用
5.2. インフラ・公共施設への応用
5.3. 製造業向けのメンテナンス管理 6.1. 要件定義と現場ヒアリングの重要性
6.3. 導入後の教育・サポート体制
6.3. 導入後の教育・サポート体制 7.1. 既存業務システムとの連携は可能?
7.2. 導入費用と運用コストの目安
1. 保守メンテナンス業務の現状と課題

現状では、保守メンテナンス業務におけるアナログ管理や情報連携の遅れが大きな問題となっています。
多くの企業が保守メンテナンス業務を紙の帳票やエクセルで管理しているため、情報の重複や更新漏れが頻発しています。このようなアナログプロセスに依存すると、現場とオフィス間での連携がスムーズに行えず、迅速な意思決定が難しくなります。
また、担当者が変わるたびに引継ぎが煩雑になるという課題も見逃せません。
加えて、固定的な方法で業務を継続しているため、リアルタイムで最新情報を共有することが困難です。設備が全国に分散しているケースや、時期ごとに点検項目が変わるケースでは、常に正確な状況把握を行う仕組みが必要です。こうした現状を改善するためには、デジタル化による全体管理が不可欠といえます。
さらに、設備故障や作業ミスに対する未然防止策を構築しにくい点も大きな問題です。過去の点検履歴や消耗品の使用状況を活用できない状態では、突発的なトラブルに対して場当たり的な対応を繰り返すことになり、コストの増加原因となります。こうした数々の課題を解決する方法として、保守メンテナンスシステムの導入が注目されています。
1.1. アナログ作業やペーパーレス化の遅れ
保守作業の計画や実績を紙やエクセルで管理していると、作業工程の変更や進捗の更新がリアルタイムに反映されにくくなります。その結果、現場スタッフが古いデータを基に作業を行い、ミスが誘発される可能性が高まります。
また、紙ベースの管理は、書類の紛失や複製に手間がかかり、すべての拠点で同じ手順や書類を共有することが困難です。ペーパーレス化が進まないことにより、管理コストの増加、検索性の低下および書類保管スペースの必要といった、さまざまな課題が蓄積されます。
こうした問題を解決するためには、クラウド上でデータを一元管理できるシステムが効果的です。必要な情報にいつでもアクセスできることで、保守作業の効率と正確性が大幅に向上します。
1.2. 現場情報のリアルタイム共有の必要性
設備の故障やトラブルは、時間との勝負になることが多いため、できるだけ早く状況を把握して対応策を講じる必要があります。
しかし、情報共有の遅れは、復旧に大きな時間的ロスを生じさせるだけでなく、顧客との信頼関係にも悪影響を及ぼします。
特に、地域が広範囲にわたるインフラ保守では、限られた要員で膨大な設備を管理しなければならず、トラブル発生時には迅速な連絡と対応策が求められます。アナログの手法では、現状報告や応援要請が遅れ、被害が拡大するリスクも否定できません。
リアルタイム共有を実現することで、現場からのステータスを即座に確認し、適切なリソース配分が容易になります。これによりトラブルの拡大を防ぎ、サービスレベルの維持や顧客満足につなげることが可能です。
2. 保守メンテナンスシステム導入の利点

システムを導入することで、作業効率やサービス品質を大幅に向上させることができます。
保守メンテナンスシステムを導入する最大のメリットは、保守業務全体を統合的に管理できることです。例えば、作業日程や準備品、作業単位ごとのチェックリストを集約することで、担当者同士の連携がスムーズになり、抜け漏れを大幅に抑えられます。
さらに、従来の紙管理やエクセル管理では把握しにくかった実績データを、自動的に蓄積・分析することが容易になります。これにより、適正な保守計画を簡単に立てることができたり、設備の劣化状況を早期に発見したりするなど、データドリブンな判断が可能です。
結果として、顧客へのサービスのクオリティが向上し、トラブル発生時の対応スピードや正確性が格段に上がります。
こうしたメリットは、企業の評価やブランディングにも直結するため、中長期的に見ても導入の効果が期待できます。
2.1. 作業効率向上と人的ミスの削減
システムの導入によって、作業指示や点検履歴の管理がデジタル化されると、作業者間の情報共有が格段にスムーズになります。従来は口頭での伝言や手書きメモでの共有が中心であり、誤記や重複作業が発生しやすい状況でした。
しかし、保守メンテナンスシステムを利用することにより、作業内容が明確化し、確認や更新がリアルタイムで反映されるため、人為的なミスが大幅に削減されます。作業完了報告も簡単に入力できるため、報告書作成などの付随業務の効率化にもつながります。
また、システムで管理された過去のデータを参照することで、同様のトラブルの対処法や必要な交換部品などをすぐに確認可能です。これにより、現場スタッフが短時間で適切な判断を下せる体制を整えられます。
2.2. データ連携と現場DXの実現
保守メンテナンスの現場DXを実現するためには、設備やセンサーからのデータを一元的に収集・分析し、それを運用や戦略に活用することが不可欠です。システムの導入により、IoT機器と連携して設備の稼働状況をモニタリングし、異常値を早期に発見するなどの高度な管理が可能になります。
さらに、システムを利用すれば、どの拠点からでも同じ情報にアクセスできるため、地域間やチーム間の情報格差を減らせます。これにより、全社的な経営戦略と現場の動きが連動しやすくなります。
リアルタイムのデータを活用することで、予兆保全や適切な資源配分といった高付加価値サービスを提供しやすくなります。結果として、システム導入によるデータ連携は保守メンテナンスの質の向上に大きく寄与します。
2.3. 顧客満足度向上につながるサービス強化
保守メンテナンスシステムを活用すると、顧客とのやり取りや情報提供が迅速化し、ブランドイメージの向上につながります。特にアフターサービスにおいては、問い合わせから解決までのリードタイム短縮が大きな差別化要因となります。
システム上で履歴を管理しておけば、過去の保守状況や契約内容を即座に参照できるため、担当者が変わっても同じレベルの応対が可能です。このような安定感は顧客の信頼度を高め、リピートオーダーや長期契約に結び付きやすくなります。
また、自社の保守管理体制が整っていることをアピールすれば、新規顧客への訴求力も高まります。その結果、サービス強化は直接的な売上向上だけでなく、企業全体の付加価値を高める効果も期待できます。
これらの機能を活用すれば、管理の手間を削減しつつ、品質や安全性を高めることが可能です。以下では、代表的な機能をさらに具体的に見ていきます。
3. 保守メンテナンスシステムの主な機能

多様な管理機能を備えたシステムにより、あらゆる保守・メンテナンス作業を統合的に管理できます。
保守メンテナンスシステムは、主に設備や作業、顧客情報を一元的に扱えることが特徴です。これにより、複数の担当者が同時に参照してもデータの矛盾が起こりにくく、効率的に業務を進められます。
また、帳票や報告書の電子化、外部システムとの連携など、業務プロセス全体をサポートする機能を含んでいるケースが多いです。
特に近年では、クラウド上で分散した現場情報をリアルタイムで共有できるソリューションが注目を集めています。
これらの機能を活用すれば、管理の手間を削減しつつ、品質や安全性を高めることが可能です。以下では、代表的な機能をさらに具体的に見ていきます。
3.1. 設備・機器管理機能
多様な管理機能を備えたシステムによって、さまざまな施設や機器に対して、型番や設置場所、保守履歴などを登録し、一元的に管理できます。紙ベースや個人のメモに頼っていると、古い情報や重複データが残りやすいですが、デジタル化によって最新情報に簡単にアクセスできます。
この機能を活用することで、設備の老朽度合いや消耗部品の交換時期を正確に把握でき、点検計画の立案や迅速な修理対応が機能的に可能になります。特に大型設備や全国に拠点が多い場合は、管理効率の向上を大いに期待できます。
さらに、機器ごとのメンテナンス履歴や事故報告を蓄積しておくことで、原因分析や長期的なコスト管理にも役立ちます。
3.2. 作業指示・スケジュール管理機能
保守メンテナンスは、担当者やチームごとに異なるスケジュールを組む必要があるため、システム上で一元管理することのメリットが大きいです。作業内容や必要な部品の在庫、現場での注意点などを一括して指示できるため、全体の把握がしやすくなります。
また、作業指示を電子化することで、変更があった場合に速やかに修正内容を共有できます。この結果、現場スタッフが常に最新の情報に基づいて作業を行い、トラブルや作業遅延のリスクを減らせます。
スケジュール管理機能が整備されていることで、スタッフの稼働率を適正化しやすく、大規模な保守対応にも余裕をもって臨むことができます。
3.3. 帳票・報告書管理機能
定期点検や修理後の報告書など、保守メンテナンス業務では多くの書類が発生します。これらを紙で管理すると、提出のたびに紙の量が増え、保管スペースの確保や情報の検索に手間がかかります。
電子化された帳票管理機能があれば、定型フォームを用意するだけで、入力から報告書の出力までを効率的に行え、書類の紛失や破損のリスクも大幅に抑えることができます。電子データは検索や集計が容易で、業務改善のための分析にも利用しやすいです。
提出先や管理レベルをシステム上で設定できることもメリットです。
3.4. 顧客・契約管理機能
保守メンテナンス業務は顧客との契約内容に基づいて進められることが多いため、顧客・契約管理機能は重要です。顧客の所在地、アフターサービス履歴、契約期間などの情報を集約して一元管理できます。
特に長期にわたる保守契約では、契約更新の時期や契約範囲の変更を適切に管理しておくことが重要です。システム上で契約アラートを設定することで、契約更新漏れによる機会損失を防げます。
また、顧客とのやり取りの履歴を記録しておくと、新しい担当者がスムーズに情報を引き継げるため、迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
3.5. 外部システム連携やデータ分析
基幹システムや会計システム、在庫管理システムなど、他のツールやプラットフォームと連携させることで、さらなる業務効率化が期待できます。たとえば、在庫情報をリアルタイムで同期すれば、部品不足による作業停滞を防ぎやすくなります。
また、IoTセンサーからリアルタイムでデータを取得し、そのまま保守メンテナンスシステム上で分析できれば、設備異常を未然に察知しやすくなります。これにより、予兆保全の精度を高め、トラブル発生リスクの低減につなげられます。
データ分析機能が充実しているシステムであれば、レポートやダッシュボードを活用して経営層への報告も効率的に行えます。
4. システムタイプ別の特徴

保守メンテナンスシステムには、対応範囲や特化領域によって異なるタイプが存在します。
企業が保守メンテナンスシステムを導入する際に、カバーしたい業務範囲によって適切なタイプが異なります。自社が必要とする機能や規模に合わせたシステムを選ばないと、導入後に使いにくさが残ることもあります。
たとえば、企業全体の基幹業務を統合し、販売管理や在庫管理を含む場合と、修理やクレーム対応に特化したアフターサービス中心で機能を強化したい場合では、選ぶソリューションが異なります。
以下では、代表的なタイプを見比べながら、どのような業務に適しているかを整理していきます。
4.1. 基幹業務統合型(販売管理・在庫管理を含む)
基幹業務統合型のシステムは、保守メンテナンスだけでなく、企業全体の業務プロセスを一括で管理することが特徴です。販売管理や在庫管理と連携することで、受注からアフターサービスまでの一貫したフローを構築できます。
このタイプを選ぶことで、部品発注や在庫状況の確認がスムーズになり、必要部品の欠品による作業遅延を未然に防ぐことが容易になります。さらに、会計システムとも連携することで、作業コストや収支の分析が簡単に行えます。
一方、機能が多岐にわたるため、導入コストや社内教育に伴う負担が大きくなる可能性がありますので、自社の規模や運用体制に合わせて検討することが重要です。
4.2. アフターサービス対応管理特化型
アフターサービス対応管理に特化したシステムは、故障対応や修理依頼、クレーム管理など、顧客接点に重きを置いた機能が充実しています。顧客満足度を向上させるためには、問い合わせ対応の履歴管理や進捗の可視化が優れていることが多いです。
また、カスタマーサポート部門と連携する機能が整備されており、電話受付やメール対応から現場担当者への引き継ぎまでをシームレスに行えます。クレーム対応の迅速化を求める企業にとっては特にメリットがあります。
ただし、販売管理や在庫管理などの機能は簡易的であることが多いため、他のシステムと連携して運用する形態が一般的です。
4.3. 活動管理向けタイプ
活動管理向けのシステムは、営業やフィールドエンジニアなどのスタッフの行動を最適化することに特化しています。地図やスマートフォンアプリと連動し、訪問予定や移動経路を効率化できるのが特長です。
また、現場での作業報告をその場でスマートフォンやタブレットから共有できるため、管理者はリアルタイムで作業進捗や問題点を把握できます。遠隔地でも同様のオペレーションが可能であることは大きなメリットです。
活動管理向けシステムは、保守メンテナンスシステムというよりは業務の効率化に重きを置いているため、設備管理機能は標準では含まれないこともあります。必要に応じて、外部システムと連携することを検討する必要があります。
5. 導入事例:業種別の活用パターン

さまざまな業種で保守メンテナンスシステムの導入が進んでおり、それぞれの業態に合った活用方法が存在します。このシステムは製造、建物管理、インフラなど多岐にわたる分野で導入されています。
具体的にどのように活用されているかを業種別に見ることで、自社への導入イメージをつかみやすくなります。業種によって、メンテナンスの頻度、必要となる設備の種類、管理の規模などが異なるため、システムに求められる機能も変化します。
代表的な活用パターンをリストアップし、自社の事業形態に近い事例を参考にしながら具体的な導入メリットや注意点を整理することで、スムーズなシステム化を進めやすくなります。
5.1. 建物・設備保全での利用
オフィスビルや商業施設などの建物管理では、空調設備や電気設備の定期点検が求められ、法令遵守の観点からも管理が重要です。保守メンテナンスシステムを活用することで、各設備の点検時期や結果を正確に登録し、忘れずに実施できます。
点検報告書もシステムで一元管理されるため、不具合が発見された際の対応状況や交換部品の履歴を簡単に遡って確認できます。これにより、建物の安全性や快適性を常に高水準に保つことが可能です。
大規模な建物群を運営する企業でも、同一システム上で複数の建物を管理できるため、全体の見通しを立てやすく、効果的に設備投資計画を策定できます。
5.2. インフラ・公共施設への応用
道路、橋梁、上下水道などの社会インフラを管理する機関においても、保守メンテナンスは重要な役割を果たします。特にインフラの老朽化が深刻化している現状では、予防保全の考え方を適切に取り入れることが必要です。
保守メンテナンスシステムを導入することで、複数の拠点に及ぶ設備情報を一元管理し、工事や点検の進捗を集約して監視できます。非常時には即時報告と指示出しが可能となり、大きな被害を抑えることにつながります。
また、長期的な保守計画を作成する際も過去の履歴データが活用でき、ゾーンごとの改修優先度や予算計画を正確に立てることが可能です。
5.3. 製造業向けのメンテナンス管理
製造業においては、生産ラインの停止リスクを最小化するために、定期的なメンテナンスや部品交換が不可欠です。保守メンテナンスシステムを導入することで、設備の稼働状況や部品の寿命情報をリアルタイムで把握し、予防保全が可能となります。
また、複数の生産拠点を有する大企業では、定期点検スケジュールを一元化し、一定の基準やマニュアルに基づいて統一的に保守作業を進めることができます。これにより、品質のばらつきを防ぎ、コスト管理の精度を向上させる効果も期待できます。
作業の進捗や異常の報告が早期に行われる環境を整えることで、不測の事態が発生した際にも迅速に対応できる体制を構築できる点は大きなメリットです。
6. 導入ステップと注意点

効果的にシステムを活用するためには、導入ステップごとに把握すべき要点と注意点があります。
導入の際には、現場の具体的な課題や要件を洗い出す「要件定義」から始めるのが一般的です。次に、最適なシステムの選定やカスタマイズを行い、実際の運用に合わせた設定を進めます。
しかし、導入後の運用がスムーズに進むかどうかは、実際に使うスタッフがシステムに慣れるか、または運用ルールが徹底されるかによって大きく左右されます。せっかく投資してもスタッフの理解が進まず、使いこなせないケースは少なくありません。
教育やサポートを手厚く行い、定期的に運用状況を見直すことで、システム導入の効果を最大化できるでしょう。
6.1. 要件定義と現場ヒアリングの重要性
まずは現場スタッフの声を丁寧に拾い、実際の保守作業や運用方法を把握することが不可欠です。机上のプランだけでは、導入後に使い勝手の悪さや余計なシステム負担が生じる恐れがあります。
ヒアリングを通じて抽出した課題をリスト化し、優先度の高い項目から改善することで、早期に効果を感じられる導入計画を立てやすくなります。システムの仕様を固める際も、現場の視点を反映することで、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。
要件定義はプロジェクト全体の方向性を決定する重要なステップであるため、十分な時間を確保して行うことが重要です。
6.2. システム選定とカスタマイズ検討
選定段階では、ベンダーやシステムごとの差別化要素をしっかり比較し、自社の要件を満たすかどうかを確認します。カスタマイズの幅や追加機能の有無も、将来の拡張性を左右するため、慎重な検討が必要です。
また、導入コストに加え、運用費用やバージョンアップの対応範囲などを総合的に考慮することも大切です。
カスタマイズを最小限にして要件を満たせるかどうか、または標準機能でどこまで対応可能かという視点で比較検討することで、無駄なコストを抑えることができます。
6.3. 導入後の教育・サポート体制
システムを導入しても、使い方を詳しく知らないスタッフが多いままでは、最大限の効果を得ることはできません。操作マニュアルの整備や実際の作業シーンを想定したトレーニングを行うことで、仕組みをスムーズに浸透させることができます。
ベンダーによっては、導入時だけでなく、定期的なアップデートやコンサルティングも含めたサポートを提供する場合があります。このようなサポート体制を活用することで、新機能への対応やトラブル発生時の復旧が格段に迅速になります。
また、導入後の利用状況をモニタリングし、定期的にチームで情報を共有する場を設けることも重要です。継続的な改善サイクルを回すことで、システムが持つ潜在能力をより引き出すことができます。
7. 導入検討の際に、よくある質問

導入を検討する際によく寄せられる質問や疑問点をまとめました。
保守メンテナンスシステムの導入は、大きな投資となるため、疑問や不安を解消することが導入成功の鍵です。クラウド型とオンプレ型の違いや既存システムとの連携など、事前に理解しておくべきテーマを整理しておくことが重要です。
また、費用面や運用面でのメリットとデメリットを明確にし、自社に最適な方法を選択するために検討が必要です。
以下では、導入時によく聞かれる内容について回答を示します。自社環境や予算に合わせて見極めるためには、関連ベンダーの情報収集や専門家の意見を参考にすることが効果的です。
7.1. 既存業務システムとの連携は可能?
多くの保守メンテナンスシステムは、APIやデータインポート機能を通じて既存のERPや会計、在庫・販売管理システムと連携が可能です。必要な連携要件を事前に整理し、ベンダーに確認することが重要です。
しかし、システム間のデータ形式が異なる場合には、カスタマイズや追加開発が必要になることもあります。そのため、費用や期間が増える可能性があるため、連携要件は早めに明確にしておくことが重要です。
円滑に連携できれば、重複入力やデータ不整合を防ぎ、一貫性のある業務基盤を構築できます。
7.2. 導入費用と運用コストの目安
初期導入費用には、ライセンス料、システム構築費、カスタマイズ費用などが含まれます。クラウド型の場合、月額や年額の利用料という形が多く、オンプレ型ではハードウェア費なども考慮する必要があります。
運用コストには、メンテナンス費用、アップデート費用、人員の教育コストなどがあります。システム規模が大きいほど、これらのコストは増加しやすいため、長期的な収支バランスを考慮して導入計画を立てることが望ましいです。
ベンダーから提示される見積りのみでなく、運用開始後に発生する可能性のあるコストも含めて、総合的に検討することが成功の鍵です。
8. まとめ・総括

保守メンテナンスシステムを活用することで、業務効率と顧客満足度を向上させることが可能です。本記事では、保守メンテナンス業務の課題から、システム導入のメリットや注意点、導入ステップを概観しました。複数のシステムタイプや利用事例を参考にすることで、自社に合った最適な解決策を見つけやすくなります。
特に、デジタル化による情報共有やデータ分析がもたらす効率化効果は非常に大きく、予防保全や迅速なトラブル対応を実現する基盤となります。顧客とのやり取りも含めた統合管理を行うことで、信頼度やブランド力の向上につながります。
保守メンテナンスシステムの導入は、一度に大きな変革をもたらすため、導入ステップと運用体制の整備をしっかり行うことが重要です。現場と経営が一体となって取り組むことで、成果を最大限に引き出すことができます。
保守メンテナンスシステムに関心がある方は、ぜひ「GrowOne メンテナンス」をご検討ください。
また、まずはお客さま台帳のシステム化から始めたいという方は、簡単に導入できるクラウドサービスの「GrowOne メンテナンス on kintone」をご検討ください。