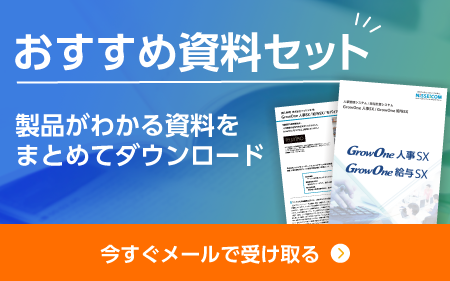退職一時金制度のすべて:仕組み・法的背景・税務まで徹底解説

2025年09月24日
退職一時金制度は、従業員の退職時に一時金を支給する福利厚生の一つであり、企業の人材戦略や従業員の将来設計に大きく関わります。
本記事では、退職一時金制度の概要や法的背景、税務上の扱い、導入メリットとデメリットなど、あらゆる観点から徹底解説します。自社に最適な制度設計のヒントとしてご活用ください。
目次
1.2. 退職給付制度(企業年金)や確定拠出年金(DC)との違い 2.1. 社内準備型と外部積立型の特徴
2.2. 退職金共済契約の範囲と被共済者間の公平な取扱い 4.1. 課税対象・退職所得控除と確定申告
4.2. 社会保険料との関係 5.1. 企業側:コスト管理と人材定着
5.2. 従業員側:将来の生活保障
1. 退職一時金制度とは

退職一時金制度の基本的な仕組みや背景を知ることで、制度導入の重要性を理解しましょう。
退職一時金制度は、法律上の義務ではなく企業ごとに任意で設計できます。しかし、福利厚生として充実させることで人材の定着や企業イメージの向上につながりやすいため、多くの企業で導入が検討されます。
退職時に支払われるまとまった資金として、従業員が将来の生活設計を立てやすくなる反面、企業としては資金繰りや運用に関するリスクを管理する必要があります。
この制度は、同じ退職金制度である企業年金や確定拠出年金(DC)とは異なり、一度に支給されることが多く、従業員側にとっては短期的な資金確保がしやすい点も特徴です。
1.1. 法第31条《退職手当等とみなす一時金》の概要
退職一時金は、労働基準法などでは直接定められていませんが、税法上は退職手当として扱われることがあります。所得税法上は退職所得として課税される可能性があり、これにより退職所得控除の適用を受けられるケースも出てきます。
企業側は、所定の手続きや文書整備を行い、退職一時金が労働の対価として認められるように、明確な支給基準を定めることが重要です。法第31条は退職金として支給される一時金の定義を示しており、ここに該当すれば、税務上も退職所得として控除が適用される仕組みです。
結果的に、法第31条の規定に基づき支給要件を定めることで、企業と従業員の双方が担税面でのメリットを得やすくなる一方、曖昧な設計をすると課税トラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
1.2. 退職給付制度(企業年金)や確定拠出年金(DC)との違い
退職金制度には、退職一時金のほか、企業年金(確定給付型や確定拠出型)があります。企業年金は年金形式で給付されることが多く、長期的な生活設計を重視する従業員に向いているといえます。対して退職一時金はまとめて受け取れるため、大きな資金が必要なライフイベントに対応しやすいのが特徴です。
企業型確定拠出年金(DC)の場合、従業員は運用内容を自ら選択して増減が決まるので、年金額が把握しにくい反面、運用成果しだいで大きく増える可能性もあります。これに対し、退職一時金は事前に定めた計算式に基づいて支払われるため、受取額がわかりやすい仕組みです。
企業にとっては、退職一時金はコスト管理や将来の支出時期が把握しやすいメリットがありますが、運用益や資金の流動性への対策は必要となります。比較検討の上で、従業員のニーズや企業の経営状況に合った制度を選択することが大切です。
2. 退職一時金制度の種類

退職一時金制度には社内準備型や外部積立型など多様な選択肢があります。特徴を知り、自社に合った制度を検討しましょう。
退職一時金制度を導入する際、どのように準備資金を確保するかが大きなポイントとなります。大まかには、社内で積み立てる社内準備型か、保険会社や金融機関などの外部機関を利用する外部積立型に分かれます。
社内準備型では、企業が自己資金で退職金原資を管理するため、流動性や運用コストの自由度が高い反面、運用リスクもすべて企業が背負うことになります。一方で外部積立型では、一定の掛金を専門機関に預けることで、企業は運用リスクを軽減できる場合があります。
退職金共済制度を利用する場合は、国や公的機関の補助も受けられるため、中小企業にとっては導入しやすい選択肢となりえます。制度設計によって、従業員の受取額や税務面での処理も違ってくるため、複数のプランを比較検討することが重要です。
2.1. 社内準備型と外部積立型の特徴
社内準備型は、自社内で資金をプールしておくため、企業が資金管理の自由度をもつ一方で、一括で大量の退職一時金が必要になった時期には資金繰りの課題が生じやすいリスクがあります。特に多くの従業員が同時期に退職する場合には注意が必要です。
外部積立型は、生命保険会社や共済組合などの外部機関に掛金を預ける形で退職金原資を準備します。企業が銘柄を選定したり運用方針を決定したりする手間が軽減され、また倒産リスクなどから従業員の退職金を守りやすい点も魅力です。
ただし、外部積立型の場合には掛金負担や手数料などのコストがかかるため、制度導入時にはこれらの経費を含めた長期的なシミュレーションが欠かせません。
2.2. 退職金共済契約の範囲と被共済者間の公平な取扱い
退職金共済制度とは、中小企業を中心に組織された共済団体が運営する退職金制度で、契約を締結した企業の従業員が対象となります。中小企業退職金共済(中退共)や特定退職金共済など、複数の共済制度があります。
共済制度では、掛金の一部を国が補助するケースもあり、企業負担を軽減できるメリットがあります。また、共済を利用することで外部での積立を確保できるため、企業が資金繰りで困るリスクを減らせます。
導入にあたっては、被共済者を選別する基準や、勤続年数、資格、職種ごとに公平な運用を行うルール作りが重要です。従業員の間で不公平感が生じないよう、制度設計に透明性を持たせることが求められます。
3. 勤続年数と退職一時金の支給時期

退職一時金は勤続年数によって金額や支給時期が左右されます。計画的な設計が重要です。
退職一時金は、企業が定める就業規則や退職金規定に基づいて勤続年数に応じて支給額を決定するケースが多く見られます。一般的には、勤続年数が長いほど退職金額が増える仕組みになります。
支給時期については、退職後1~3か月以内に支払う企業が多い一方で、業績やキャッシュフローの都合で柔軟に設定する場合もあります。従業員にとっては受け取りまでの期間が生活設計に影響を与えるため、明確に規定しておくことが重要です。
さらに、数年にわたり分割で支給するパターンを選択できる場合もあります。企業としては一時的な資金負担を抑えられますが、従業員側が希望する資金形態と合わないこともあるため、事前の周知と同意が必要になります。
4. 退職一時金の計算方法と注意点

退職一時金の計算には、税務や社会保険の扱いなどの重要なポイントが含まれます。
退職一時金は給与と異なる課税方法が適用されるため、計算の仕組みや税金の取扱いを正しく理解することが重要です。特に退職所得控除をはじめとする控除制度によって実際の課税額が大きく変わるため、従業員側にも正確な情報提供が必要になります。
また、社会保険の対象となるかどうかについても、制度設計や受給タイミングによっては注意が必要です。一般的に、退職金に対しては厚生年金や健康保険などの社会保険料の対象外ですが、対象となる給与との線引きが曖昧な場合、トラブルに発展する可能性があります。
4.1. 課税対象・退職所得控除と確定申告
退職一時金は退職所得として取り扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が適用されます。具体的には、勤続年数×40万円(20年超えた部分は70万円)といった定めに基づき算出され、総所得から差し引かれるため、課税対象額が大幅に減少するケースも多く見られます。
通常、退職所得に対しては源泉徴収が行われ、一時金の受取時点で所得税が差し引かれるため、原則として確定申告は不要です。ただし、源泉徴収が過大となった場合は、確定申告をすることで還付を受けられる場合があります。
退職所得控除の適用は、所定の手続きにより申請します。企業が事前に退職所得の源泉徴収票などを正しく発行し、従業員の税務手続きをサポートすることで、混乱を防ぐことができます。
4.2. 社会保険料との関係
退職一時金は一般的には給与の一部ではなく、退職金として取り扱われるため、社会保険料の算定基礎とは切り離されることが多いです。したがって健康保険や厚生年金保険などの保険料計算の対象から除外されます。
ただし、退職前に支給される特別手当や、退職金とは別に支給される一時金が給与として扱われる場合には社会保険料が課されることがあります。退職金規定の内容や支給タイミングが影響するため、制度設計時には明確に区別しておく必要があります。
社会保険との関係が不明瞭なまま退職を迎えると、従業員の負担が想定以上に増える恐れもあるため、企業としても十分に確認しながら運用することが大切です。
5. 退職一時金制度導入のメリット・デメリット

退職一時金制度を導入することで生じる、企業側と従業員側のメリット・デメリットを整理しましょう。
退職一時金制度を導入すると、企業は人材定着や従業員満足度の向上に繋がります。一方で、自己資金をしっかりと管理・運用しなければ、退職金支払い時にキャッシュフローが逼迫するリスクも存在します。
従業員にとっては退職時にまとまった資金を受け取ることができるため、将来への備えや大きな出費に対応しやすい点が魅力です。しかし、大きな資金を一括で受け取ることで使い方を誤るリスクもあるため、適切な活用計画が求められます。
5.1. 企業側:コスト管理と人材定着
企業が退職金原資をきちんと積み立てておけば、従業員の勤続意欲を高め、優秀な人材を確保しやすくなります。また、退職一時金制度は他社との差別化にもつながり、採用面でもアピールポイントとなるでしょう。
一方で、急な退職者増加で大きな退職金支払が必要となった場合、企業のキャッシュフローに影響が出る可能性があります。特に経営が安定していない場合には、管理を誤ると資金難に陥るリスクが高まります。
事業の規模や従業員の構成を踏まえ、中長期的な視点でコストを設定し、適切な準備措置をとることが重要です。
5.2. 従業員側:将来の生活保障
従業員にとって、退職一時金制度があることで退職後の大きな支えになると同時に、急な出費や新たな投資に使えるまとまった資金を得られます。特にマイホーム購入や転職準備資金など、ライフイベントへの対応がしやすくなる点は大きなメリットです。
ただし、一度に多額の資金を受け取ると、その運用方法に失敗したり、計画性なく使ってしまったりするリスクもあります。結果的に老後の生活資金が十分に確保できなくなる可能性もあるため、受け取り方やその後の資金プランには注意が必要です。
また、退職金制度が充実している企業を選ぶかどうかは、就職や転職時の大きな要素となります。自分のライフプランに合った退職金制度を備えた企業に身を置くことで、将来の不安を軽減できるでしょう。
6. 退職給付金支給事業と掛金の取り扱い

退職給付金を安定的に支給するためのビジネスモデルや掛金の取り扱い方を確認します。
退職一時金は企業の資金繰りに大きな影響を与えるため、あらかじめ十分な積立と掛金の管理が重要です。社内で積み立てる場合も、外部専門機関を利用する場合も、想定される退職者数や支給タイミングに応じて、掛金を適切に算定する必要があります。
中小企業退職金共済制度などを利用すれば、従業員の掛金を効率的に積み立てられ、国の助成を活用できるケースもあります。制度設計によっては支給時点での企業負担が大幅に軽減されることもあるため、複数の制度を比較検討して導入を決めることが大切です。
また、掛金の取扱いには税務上の経費として計上できる点が大きく、企業の損益計算においては有利に働く場合があります。ただし、法令や通達による制約もあるため、専門家と連携しながら正しい手続きを踏むことが求められます。
7. 退職一時金規定を整備するポイント

実際に自社で退職一時金規定を策定する際の留意点や具体的な策定手順を紹介します。
退職一時金規定を作成する際、まずは支給対象者の範囲、支給額の決定基準、そして支給形態などの基本的な項目を明確にします。特に正社員のみ対象とするのか、一部の契約社員やパート社員も含めるのかなど、公平性の観点から検討が必要です。
次に、支給のタイミングや手続き方法も明記しておくと、従業員が申請しやすくなり、トラブルの発生を防げます。退職一時金の源泉徴収についても、規定内で分かりやすく説明することが大切です。
最後に、就業規則や労働協約などの他の関連規定との整合性を確認しながら、必要に応じて見直しを行うプロセスを整えておきましょう。定期的なメンテナンスを行うことで、時代の変化や法改正に対応し、従業員の満足度を維持できます。
8. 関連制度・参考資料

退職一時金制度をさらに深く理解するために役立つ関連制度や参考資料を一覧で確認できます。
退職金の制度は多岐にわたるため、厚生労働省や国税庁の公式サイトなど、信頼性の高い情報源を参照することが大切です。また、中小企業退職金共済制度の公式ウェブサイトでは、具体的な掛金や給付額のシミュレーション、導入手順が詳しく説明されています。
企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)など、他の制度と組み合わせて導入することで、従業員のライフプランに対応しやすい退職金制度を構築できます。専門家のセミナーや研修に参加し、最新の情報を常にアップデートしておくと良いでしょう。
また、専門サイトや専門家による解説書なども参考になります。導入にあたっては、社内合意形成と専門家のアドバイスをバランスよく取り入れることが重要です。
9. まとめ:自社に合った退職一時金制度を選択しよう

自社の状況や従業員のニーズを踏まえ、最適な退職一時金制度を検討し、将来的な安定と安心を確保しましょう。
退職一時金制度は、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットがありますが、制度設計を誤ると、資金繰りや税務でトラブルとなる可能性もあります。まずは目的や財務状況、従業員規模を踏まえ、どの形態が最適かを検討しましょう。
退職一時金だけでなく、企業型確定拠出年金(DC)や中小企業退職金共済制度など、さまざまな選択肢を比較検討することで、より幅広いニーズに対応できる制度設計が可能になります。専門家や他社事例から学びながら、従業員が安心して退職後の生活を送るための土台を作りましょう。
長期的な視点を持つことで、退職金制度の導入は企業の信頼性向上と、従業員の満足度向上につながります。ぜひ、自社に合った退職一時金制度を導入し、安定した事業基盤を築いてください。