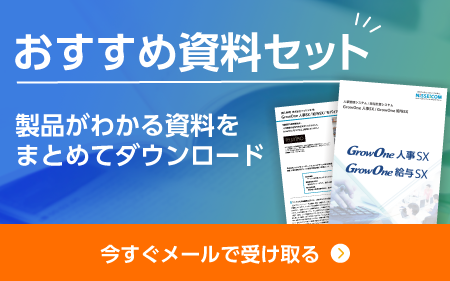定期昇給のすべて ~仕組み・計算方法・メリット・注意点を徹底解説~
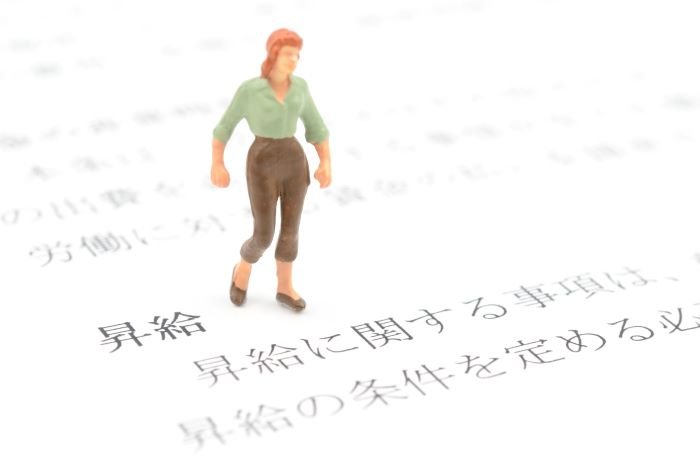
2025年09月24日
定期昇給とは、企業が設定した時期に合わせて従業員の給与を引き上げる制度ですが、会社ごとに昇給の基準や頻度は異なります。
本記事では、定期昇給の基本的な仕組みからベースアップや昇格・昇進などの別の制度との違い、さらに運用や廃止における注意点までを総合的に解説します。まずは概要を理解し、自社の状況に合った運用のヒントを探っていきましょう。
目次
1.2. 必ず昇給するわけではない点に注意 2.1. ベースアップ(ベア)との違い
2.2. 昇格・昇進・臨時昇給などその他の昇給制度との違い 3.1. 大企業と中小企業の昇給相場
3.2. 年齢・勤続年数による違い 4.1. メリット:モチベーション向上・人材確保
4.2. デメリット:人件費負担・形骸化のリスク 5.1. 昇給率の計算式
5.2. 具体的な昇給額の算出例 6.1. 昇給の評価基準の策定
6.2. 就業規則への明記と従業員への周知
6.3. 予算管理と定期的な見直し 7.1. 不利益変更にあたる場合のリスク
7.2. 一定年齢到達による昇給停止は可能か 8.1. 福利厚生や手当の充実
8.2. キャリア支援や教育制度の整備
1. 定期昇給とは何か

まずは定期昇給の基本的な考え方と注意点について押さえておきましょう。
定期昇給は、企業があらかじめ設定した時期(多くの場合は年1回や年2回)に、従業員の給与を一定額または一定率で引き上げる制度です。一般的には勤続年数や職務内容、年齢などを考慮しながら決まりますが、会社によっては評価結果も加味されることがあります。従業員にとっては将来的な収入見通しが立ちやすく、企業にとっては人材定着や採用競争力の向上に役立つとされています。
一方で、定期昇給を維持するには一定のコストが発生するため、企業の業績に大きく影響される面も存在します。制度設計や運用が曖昧だと、従業員のモチベーション向上に結びつかないだけでなく、人件費負担が増大するリスクも出てきます。そこで、きちんと評価基準を設定し、透明性のあるコミュニケーションを図ることが大切です。
1.1. 定期昇給の定義と目的
定期昇給は、あらかじめ決められたタイミングで従業員の給与を上げる仕組みを指します。多くは企業の就業規則や評価制度に明記され、昇給の判断基準には年齢や勤続年数、スキルの習得度合いなどが含まれます。こうした定期的な昇給は、従業員の生活安定を図ると同時に、職場へのロイヤルティやモチベーションを高める目的で導入されることが多いです。
特に日本では昭和初期から本格的に導入され、多くの企業で定着してきました。最近では、成果主義の要素も取り入れながら、ベースとなる定期昇給を維持する企業も少なくありません。企業としては、ある程度の昇給を見込めることで長期的なキャリア形成を支援し、熟練した人材を安定的に確保する狙いがあります。
ただし、運用側は「定期的」に昇給があることをどのように従業員に伝えるか、そして実際の昇給幅をどう決めるかが重要です。曖昧な運用では逆に不公平感を招きやすく、人材流出を引き起こす原因にもなり得ます。
1.2. 必ず昇給するわけではない点に注意
定期昇給と言っても、会社の業績や個々の評価結果によっては、実施が先送りされたり昇給額が低く抑えられたりする可能性があります。多くの企業では「業績連動型」の仕組みや、一律ではなく個別評価を反映させる仕組みを採用しているため、定期"的"に行われるとはいえ絶対ではありません。
不況時や経営状況の悪化時には、定期昇給そのものが停止するケースも見受けられます。また、就業規則に定期昇給に関する条項があっても、実際には成果主義に移行している企業もあり、その場合は昇給水準に大きな差が出ることがあるのです。従業員としては、自分の勤務先の制度をしっかり理解し、日々の評価に対して意識を高めておくことが望ましいでしょう。
企業側も定期昇給を「義務」と誤解されないように注意すべきです。就業規則や労働契約書の文言を明確にしておくことで、トラブルを回避できる可能性が高まります。
2. 定期昇給とベースアップ・昇格・昇進などとの違い

定期昇給と他の昇給制度は混同されがちですが、それぞれに特徴があります。
昇給という言葉は一括りにされがちですが、実際にはさまざまな種類が存在します。定期昇給は企業が決めた時期に応じて個々の給与を上げる仕組みであり、ベースアップ(ベア)は企業全体の基本給を一律に上げる施策が中心です。さらに、昇格・昇進は役職や職位のランクが上がることで給与体系が変化する場合を指すなど、それぞれ目的や基準が異なります。
こうした違いを理解することは、従業員が自分のキャリアプランを描く際にも非常に重要になります。特に、定期昇給では成果が大きく反映されない場合もある一方、昇進や昇格では成果や適性が大きく評価されるのが特徴です。ベースアップは全体の給与水準を底上げするものなので、制度の狙いと仕組みを区別しておきましょう。
2.1. ベースアップ(ベア)との違い
ベースアップ(ベア)は、会社全体の基本給水準を一律に引き上げる制度です。一般的に労働組合の要求や会社の方針として交渉が行われることが多く、企業業績や将来見通しを踏まえた判断によって決定します。定期昇給が個々の能力や勤続年数などを考慮するのに対して、ベアは全従業員の底上げを狙う点が特徴です。
たとえば、経営陣と労働組合が「基本給を3%上げる」などと合意した場合は、全従業員の月給が一律に3%増加します。一方、定期昇給では個人ごとに昇給額が異なることが多く、その差が大きい場合もあります。ベアは企業の経営姿勢を示しやすく、景気への影響も注目されやすい制度ですが、個々の評価は反映されにくいという側面があります。
2.2. 昇格・昇進・臨時昇給などその他の昇給制度との違い
昇格や昇進は、職位や役職が上がることで給与テーブルも変更され、結果として昇給が起こります。これは定期昇給というよりも、人材の能力向上や組織再編などに応じた人事施策といえます。臨時昇給は、特別な功績を上げた場合や急な人材需要が出た場合に、通常時期とは別に給与を上げる制度を指します。
こうした制度は、定期昇給と併用されることもあり、企業ごとに運用ルールが異なります。社員としては「いつ・どんな成果が評価されるのか」を理解しておくことが大切です。企業側も、複数の昇給制度を適切に使い分けることで、人材育成とモチベーション維持に役立てることができます。
3. 平均昇給額と昇給率の目安

企業規模や年齢、勤続年数によって昇給額や昇給率の相場は異なります。
定期昇給を考える際に気になるのが、平均的な昇給額や昇給率です。大まかな目安として、月給ベースで5,000円程度、あるいは2%前後の昇給率が一般的とされています。ただし、これはあくまで統計上の平均値であり、企業規模や業種、また個人の評価状況によっても大きく変わる点に注意が必要です。
大手企業では比較的昇給額が高い傾向があり、中小企業ではスキルや成果が顕著に昇給に反映されるケースもあります。実際には、企業がどの程度予算を確保できるか、また景気や業績の動向がどれだけ影響を与えるかが重要なポイントとなります。
3.1. 大企業と中小企業の昇給相場
一般的に、大企業は業績が安定している・従業員数が多いなどの理由から、平均的に高い昇給額を設定する傾向があります。一方で中小企業は業績の変動を受けやすいため、昇給額や昇給率にばらつきが生じがちです。ただし、中小企業の中には特定の業種で高収益をあげている場合など、独自路線で手厚い昇給を行う例も存在します。
大企業でも、景気後退期には昇給率を抑制する動きが見られることがあります。逆に業績好調な中小企業だと、従業員の士気を高める目的でしっかりと定期昇給を実施するケースもあります。会社の規模だけでなく、業績や経営方針を含めて総合的に見ることが大切です。
3.2. 年齢・勤続年数による違い
年齢や勤続年数が上がるにつれ、昇給額も高くなる傾向があります。日本の企業文化では、長く在籍することで賃金が伸びる年功序列的な考え方が根強いからです。ただし近年は、成果主義や職務給を導入する企業が増えており、必ずしも年齢によって自動的に昇給するわけではありません。
また、役職や専門職のキャリアが進むほど、昇給の幅やペースが上がる場合もあります。逆に、一定年齢を超えると昇給が減少する企業もあり、どのタイミングでどのくらい給与が上がるかを知っておくことはキャリア形成上重要と言えます。
4. 定期昇給制度を導入するメリット・デメリット

定期昇給を実施することで得られるメリットや、想定されるリスクを整理します。
制度を良好に運用すれば、従業員に「給与が未来に向かって増えていく」という安心感を提供できます。結果としてモチベーションが向上し、長期的な人材の定着率が高まるのが大きなメリットと言えます。一方で、制度が形骸化すると、企業の人件費負担が無制限に増え続ける可能性があります。
メリットとデメリットをしっかり把握した上で、自社の事業内容や財務状況に見合った制度設計を行うことが重要です。特に、景気の変動など外的要因が企業の収益に与える影響をどのように織り込むかを明確にしておく必要があります。
4.1. メリット:モチベーション向上・人材確保
定期昇給によって、将来的に収入が増える見込みが立つと、従業員は安心して仕事に取り組むことができます。ライフプランやキャリアプランを描きやすく、仕事へのモチベーションも高まるでしょう。また、採用活動の際にも給与制度が明確であれば、人材獲得に有利となります。
企業にとっては、熟練した人材を社内に蓄えることが可能になるため、組織力の向上を期待できます。制度が機能していると、会社全体として「長く働けば必ず評価される」という風土が定着しやすいのです。
4.2. デメリット:人件費負担・形骸化のリスク
定期昇給はその性質上、従業員が増えるほどトータルの人件費が右肩上がりに増加していきます。会社の業績が安定している間は問題になりにくいですが、不況や予想外の経営悪化が起こった場合に対応が難しくなるリスクがあります。
また、定期昇給が「当たり前」となると、一部の従業員にはモチベーションの上昇につながらないことがあります。昇給の評価基準が曖昧だと、成果を出しても報酬に反映されにくいと感じる人も出てくるでしょう。これが行き過ぎると、制度が形骸化して企業活力を損なう恐れがあるため注意が必要です。
5. 定期昇給の計算方法と設定ポイント

昇給率や昇給額の具体的な計算例と、設定時に押さえたいポイントを紹介します。
定期昇給を導入する際は、どのように昇給率や昇給額を計算するのかが重要になります。自社の給与テーブルや就業規則に合わせて決定し、従業員へわかりやすく説明できる基準を設けることが理想です。特に昇給率の設定は企業の財政状況に直結するため、綿密なシミュレーションが求められます。
給与の基本給が大きいポジションほど、同じ昇給率でも昇給額が大きくなる特徴があり、評価や能力差が結果にも顕著に表れます。こうした事情を踏まえると、企業は昇給額の上限や評価基準の透明性を保つ仕組みを整備する必要があります。
5.1. 昇給率の計算式
一般的に昇給率は、(昇給後の基本給 - 昇給前の基本給)÷ 昇給前の基本給 × 100%という式で表されます。たとえば昇給前の基本給が25万円で、昇給後の基本給が25万5,000円の場合、(25万5,000円 - 25万円)÷ 25万円 × 100%=2%が昇給率となります。
この計算式により、自社の予算内でどの程度昇給させられるかを明確にできるため、予算管理には欠かせない指標となります。同時に、人件費全体のシミュレーションも合わせて行い、将来的な影響を見込んでおくことが大切です。
5.2. 具体的な昇給額の算出例
先ほどの例でも触れましたが、基本給が25万円で昇給率を2%と設定した場合、実際の昇給額は5,000円になります。これにより昇給後の給与は25万5,000円をベースとし、残業代や各種手当の計算にもこの新しい基本給が反映されていく形です。
もし昇給率を1%上げると、昇給額はさらに上積みされることになるため、企業の人件費は大きく変動します。こうした数値モデルを複数パターンで検討し、自社に最適な昇給率を見極めることが制度設計の肝となります。
6. 定期昇給制度の導入・運用の流れ

導入には評価基準や就業規則の整備、予算管理の検討が必要です。
定期昇給制度を導入する際には、まず評価基準の策定や就業規則への明記といった基本的なステップを踏むことが重要です。従業員が昇給の根拠や計算方法を把握できるようにすることで、納得感が高まりスムーズな運用につながります。評価プロセスや昇給時期を明確にしたうえで、予算管理と運用サイクルの見直しを継続的に行うことが有効です。
特に評価基準については、定量化しやすい成果指標と、定性的な要素をバランスよく組み合わせると、従業員が多面的に評価されやすくなります。就業規則への明記を怠ると、残業代や休日手当の基準が不透明になりやすいため注意が必要です。
6.1. 昇給の評価基準の策定
定期昇給をスムーズに行うには、明確な評価指標が欠かせません。売上や利益などの定量的な成果だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力など定性的な要素も評価に入れることで、公平性が高まります。あらかじめ評価ランクを複数用意し、従業員にはその評価ごとにどの程度の昇給が期待できるかを示すと良いでしょう。
また、評価基準は定期的に見直すことをおすすめします。時代の変化や事業内容の転換に伴い、求められるスキルや行動指針が変わる場合があるため、柔軟にアップデートしていくべきです。
6.2. 就業規則への明記と従業員への周知
定期昇給の有無や適用条件は、就業規則に明記しておくことで、法的にも会社としての立場を明確にできます。従業員が安心して働くためには、制度の存在だけでなく、その運用ルールや例外事項についても十分に説明しておくことが望ましいです。
周知には社内イントラネットや説明会、個別面談などが活用されることがあります。特に新入社員や中途入社社員に対しては、入社時へ説明を行うことで早期に企業文化や昇給制度を理解してもらうことができます。
6.3. 予算管理と定期的な見直し
企業が定期昇給制度を継続していくうえで、毎年の予算編成が大きな課題となります。人件費総額が増加していくことを見越して、収支バランスの維持や利益率の確保に向けた経営戦略を進める必要があります。定期的に財務状況をチェックし、必要に応じて昇給率や昇給額の見直しを行うことが大切です。
見直しの際は、従業員代表や労働組合との話し合いを行い、相互理解を深めながら合意形成を図ることが望ましいでしょう。制度の安定運用には、こうしたコミュニケーションが不可欠となります。
7. 定期昇給制度の廃止・停止における注意点

制度を廃止・停止する際のリスクや法的側面を見極める必要があります。
企業の経営環境や人事方針の変化によっては、定期昇給制度の廃止・停止が検討されることもあります。廃止や停止に踏み切る場合、就業規則の不利益変更と見なされる可能性があり、従業員との間でトラブルが生じやすい点に注意が必要です。特に整理解雇など、大規模な人事再編とセットで行われる場合は慎重な対応が求められます。
合理的な理由や従業員側の合意を十分に得ないまま制度を廃止すると、裁判などの法的リスクに発展するケースもあります。まずは専門家の助言を受けつつ、従業員への説明や代替策の提示を丁寧に行い、スムーズな移行を図ることが不可欠です。
7.1. 不利益変更にあたる場合のリスク
定期昇給制度が就業規則や労働契約書に明記されている場合、その撤廃は労働条件の不利益変更に該当し得ます。労働条件の変更には、合理性や従業員の合意が求められるため、曖昧な説明や一方的な決定はトラブルの火種になります。
万一、従業員から反発が起きた場合には、労働審判や訴訟に発展する可能性もあります。企業は廃止の必要性や代替措置をしっかり提示し、対話の場を確保することで法的リスクを最小化することが重要です。
7.2. 一定年齢到達による昇給停止は可能か
一定の年齢に達した場合に昇給を停止する制度は、年齢差別と捉えられる恐れがあるため注意が必要です。法的には合理的な理由がある場合に限り認められる可能性がありますが、具体的な業務内容の変化や、企業全体の賃金設計との整合性を示す必要があります。
何ら根拠のないまま年齢だけを理由に昇給を打ち切ると、従業員の不満や苦情が相次ぎ、コンプライアンス違反にもつながりかねません。導入を検討する際は、専門家への相談を行い、制度の妥当性を十分に検証することが大切です。
8. 定期昇給以外の従業員サポート策

定期昇給の有無にかかわらず、従業員をサポートするさまざまな方法があります。
定期昇給だけが従業員を支援する手段ではありません。福利厚生の充実や各種手当、教育制度の拡充など、多様なアプローチで従業員をサポートすることができます。これらの制度が総合的に機能することで、従業員の働きやすさや満足度が大きく向上し、生産性も高まると考えられます。
昇給にばかり注力すると、企業としては人件費が高騰しやすい半面、他の面でのサポートが充実していないと従業員満足にはつながりにくい可能性があります。したがって、バランスよく制度を整え、従業員の多様なニーズに応えていくことが理想的です。
8.1. 福利厚生や手当の充実
住宅手当や家族手当、通勤手当など、生活面のサポートを充実させることで、従業員の経済的負担を軽減できます。これにより定期昇給が多少抑えられても、従業員の実質的な生活水準を下げずに済むケースが多いです。
企業イメージの向上にもつながるため、福利厚生や手当に力を入れる企業は増えています。特に子育て支援や時短勤務などの制度は、ワークライフバランスを重視する層にとって魅力的です。
8.2. キャリア支援や教育制度の整備
従業員のスキルアップとキャリア形成を支える教育制度も、重要なサポート策の一つです。研修やセミナーの充実、資格取得支援などを行うことで、従業員は自らの能力を高められ、企業としても生産性やイノベーションを促進できます。
定期昇給に限らず、スキルアップを重視する企業は人材の定着率が高くなる傾向があります。さらに、学んだ知識を新しい事業や既存業務の改善に生かすことで、中長期的な企業成長にも寄与します。
9. まとめ・総括

定期昇給制度は従業員のモチベーション向上や企業の長期的成長に寄与しますが、導入・運用には慎重な検討と見直しが必要となります。
定期昇給は、企業と従業員の双方にとってメリットがある一方で、安易な設計や運用はトラブルを引き起こすリスクがあります。ベースアップや昇格・昇進などの制度との違いを正しく理解し、企業の方針や経営状況に合った仕組みを構築することが大切です。とりわけ、評価基準や就業規則を整備し、従業員との丁寧なコミュニケーションを図ることで、制度の効果を最大化し、不必要な摩擦を避けることができます。
また、廃止・停止の際の不利益変更リスクや法的な観点も軽視できません。企業としては、制度の導入時から見直しのシナリオまで考慮しつつ、福利厚生や教育制度と組み合わせたトータルの人材育成策を展開しましょう。定期昇給の有無だけでなく、従業員が安心して働ける環境づくりや、長期的なキャリア形成の支援を行うことで、企業全体の成長を着実に進めていくことができます。