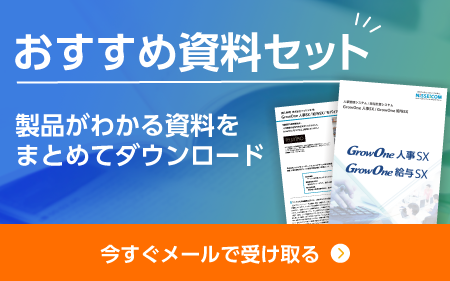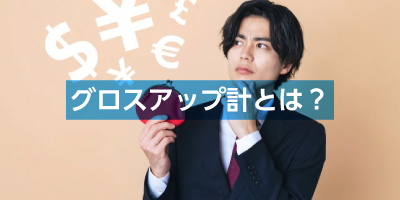給与の日割り計算とは? 基本ルールから実務対応まで総合解説

2025年09月24日
給与の日割り計算は、従業員の入社・退職や欠勤などの状況に応じて、働いた日数や時間分の給与を公正に算出するために欠かせない仕組みです。
本記事では、給与の日割り計算に関する基本的なルールから、代表的な計算方式、手当・控除の扱い方、最低賃金の兼ね合いなど、さまざまな視点で解説します。実務対応のポイントを押さえて、企業と従業員の両方が安心して働ける環境づくりを実現していきましょう。
目次
2.2. 欠勤・休職・早退・遅刻の場合 (1)暦日数方式
(2)所定労働日数方式
(3)月平均所定労働日数方式
(4)実労働日数方式 4.1. 通勤手当や定額手当の取り扱い
4.2. 固定残業代と時間外手当の計算
4.3. 社会保険料・税金は日割りになる? 5.1. 計算方法の一貫性と透明性
5.2. 不利益変更を回避するためのポイント
1. 給与の日割り計算に関する法律や規定の概要

給与の日割り計算そのものを直接的に規定する法律はありませんが、合理的かつ公正な方法を企業が独自に定めることが求められます。
賃金支払いに関する基本的なルールは労働基準法によって定められていますが、日割り計算の仕組みについては明確な法的指針は提示されていません。そのため、企業ごとに就業規則や賃金規定で計算方法を定め、従業員にわかりやすく説明することが重要です。
公正な日割り計算を行う際には、あらかじめ労使で協議し、納得のいく水準を設定することが望ましいです。また、計算方式を変える場合には、従業員の不利益にならないよう配慮し、必要な手続きを踏むこともトラブル防止に欠かせません。
2. 給与の日割り計算が必要となるタイミング

給与を日割りで計算するのは、従業員の勤務実態に変動が生じるケースが中心です。
企業では、毎月定額の給与を支給する月給制が多く採用されていますが、実際の就労状況が変動する場合は日割りで対応します。特に、途中で入社したり退職したりするケース、欠勤や休職によって勤務日数または時間が大きく変わるケースなどで日割り計算が必要です。
この計算が行われるタイミングを正しく把握し、効率よく給与を算定することで、企業側の事務負担や従業員の不信感を減らすことができます。次に挙げる具体的なケースごとに、どのように対応すべきか確認しましょう。
2.1. 中途入社や途中退職の場合
従業員が月の途中で入社・退職をする場合、その期間に勤務した日数や時間に応じて給与を算出する必要があります。例えば、基本給を週や日ごとに分割して支給するなど、就業規則で定めた方法に沿って正確に計算するのが原則です。
この際、社会保険や雇用保険の加入時期や離職日との関係も意識しながら支給額を決めると、トラブルを回避しやすくなります。日割り計算で不足が生じたり、逆に過払いが発生したりすることがないよう、勤怠管理や書類の整合性を常にチェックしましょう。
2.2. 欠勤・休職・早退・遅刻の場合
労働日数や労働時間が所定よりも短くなった場合、欠勤や休職、早退・遅刻などの発生時間や日数を考慮したうえで、給与を日割りまたは時間割りで計算する必要があります。ここでも、どのように分母と分子を設定するかは企業の裁量に委ねられていますが、公平性を保つことが重要です。
特に、休職が長期に及ぶ場合は、就業規則に定めた支給停止基準や日割り計算のルールがかかわります。従業員に適切に説明し、算出基準を理解してもらうことで、後々のトラブル防止に役立ちます。
3. 代表的な給与の日割り計算方法

日割り計算には複数の方式が存在し、企業によって採用される方法はさまざまです。
どの方式を選ぶかは、自社の就業形態や労働時間管理の考え方で決まります。暦日数をベースにするか、所定労働日数をベースにするかなど、各社が採用する方式は異なるものの、公平性や計算のしやすさを考慮して選択することが大切です。
以下では、主な4つの日割り計算方式を解説します。自社に最も合った方法を選定するための判断材料として活用してください。
(1)暦日数方式
当月のカレンダー上の日数(暦日)を分母にして、実際に勤務した日数をもとに計算する方式です。暦上の全日数で割り出すため、事務的には単純で扱いやすいというメリットがあります。
しかし、月によって暦日数が異なり、勤務実態に比べて日給が変化しやすい点に注意が必要です。従業員が多い会社で採用する場合は、月ごとの日数の違いが不公平感につながらないよう、周知と説明が欠かせません。
(2)所定労働日数方式
企業が定める所定労働日数をベースに、従業員が実際に働いた日数に応じて給与を計算する方式です。営業日数が分母となるため、勤務実態に近い形で日割り給与を算出しやすいという特徴があります。
一方で、祝日や休日が多い月と少ない月の差が大きいと、給与格差が生じる可能性もあるため、従業員に対してルールやメリット・デメリットをしっかり説明することが重要です。
(3)月平均所定労働日数方式
1年間の総労働日数を12か月で平均化し、その平均日数を分母とすることで、月によるばらつきを緩和して計算する方式です。季節や祝日によって変動しがちな所定労働日数を全体でならすため、従業員が受け取る給与額が一定化しやすい傾向にあります。
ただし、実際に働いた日数とのバランスに差が出やすい点もあるため、企業は分母の設定根拠を就業規則や説明資料で明確にしておくことが大切です。
(4)実労働日数方式
従業員が実際に働いた日数や時間を、労働契約上の所定労働との比較で日割り算出する方法です。日々の勤怠管理が厳格であれば、最も現実的な数字に即した支給が可能になります。
ただし、勤怠データの管理が不十分な場合には算出ミスを起こしやすいため、しっかりとシステム導入や管理体制を整える必要があります。
4. 手当・控除の扱いポイント

給与の日割り計算でしばしば問題となるのが、各種手当や控除の取り扱いです。
基本給と異なり、手当はその性質によって支給の形態が異なります。例えば、住宅手当や家族手当などは生活の補助的な意味合いが強く、単純計算では調整が難しいこともあります。就業規則で「日割り対象とするのか、満額支給とするのか」を明示しておけると、安全かつ分かりやすいです。
また、社会保険料や税金の控除は月単位が基本となるため、日割り計算の内容によっては誤差が生じやすい点にも注意が必要です。これら手当・控除に対してどう対応するかをしっかり決め、実務上の漏れがないように管理しましょう。
4.1. 通勤手当や定額手当の取り扱い
通勤手当は従業員が出勤するための費用を補う性質があり、多くの企業で定額支給が行われています。日割り計算の対象にするかどうかは、従業員の通勤形態やコスト負担の実態を踏まえ、就業規則で明確に決めることがポイントです。
定額手当(例えば役職手当など)については"勤務実態があってこそ"という考えのもと、短期間の勤務でも減額対象にしない企業も存在します。どちらの場合も、支給対象や支給基準を事前に全員へ共有することで混乱を防ぎます。
4.2. 固定残業代と時間外手当の計算
固定残業代は、一定の残業時間を見込んであらかじめ給与に含める形態ですが、日割り計算する場合は注意が必要です。固定残業代の対象となるのは所定の残業時間に見合う金額であり、予定を超える分については別途追加の時間外手当を支給するべきです。
日割りでの固定残業代の扱いを誤ると、実際の残業時間よりも不当にカットする結果となりかねません。就業規則に詳細を記載し、計算過程や追加支給の有無を従業員全体に周知徹底することで誤解を防ぎます。
4.3. 社会保険料・税金は日割りになる?
社会保険料や源泉所得税は月単位で計算・徴収されるのが基本です。そのため、日割り計算の給与額と社会保険料の水準が必ずしも一致しないケースがあります。
特に給料が大幅に減った月でも社会保険料は一定額となる場合があるなど、従業員の負担が増減しやすい点を配慮する必要があります。最終的には法律や条例に沿って賃金と社会保険料を切り分けることが望ましく、就業規則で周知しておきましょう。
5. 就業規則で明記すべき内容と従業員周知の重要性

給与の日割り計算を円滑に進めるためには、企業の就業規則で明確なルールを定め、周知することが欠かせません。
就業規則で明らかにするべきポイントは、どの方式で日割り計算を行うか、どのような手当が日割りの対象になるか、公正な計算が行われるかどうかなどです。これらを曖昧にしてしまうと、後から計算が変わってしまったり、従業員に不利益が生じたりするリスクがあります。
また、従業員への周知方法としては、イントラネットやマニュアル、研修などを活用し、全員が容易にアクセスできるようにしておくことが望ましいです。従業員に正しく理解されれば、給与トラブルを大幅に防げます。
5.1. 計算方法の一貫性と透明性
日割り計算の方式は、可能な限り一貫性を保つことが大切です。例えば、暦日数方式と所定労働日数方式をケースによって使い分ける場合、従業員に説明責任が生じやすくなります。
不明瞭さを避けるためにも、計算方式を固定し、すべての従業員に対して同一の基準を適用することが望ましいです。万一、短期間だけ例外的なルールを設ける場合は、その正当性をきちんと示すことが必要になります。
5.2. 不利益変更を回避するためのポイント
給与計算方式の変更が従業員に不利に働く場合、その変更は労働条件の不利益変更とみなされる恐れがあります。労働契約法や就業規則の規定に沿った正当な手続きと従業員の同意がなければ、トラブルに発展するリスクが高いです。
変更を行う際は、根拠と内容を丁寧に説明し、従業員側にも十分な検討時間を与えることが求められます。公平感を重視して進めれば、不利益変更による摩擦を最小限に抑えられます。
6. 最低賃金との兼ね合いとトラブル防止策

日割り計算によって、結果的に時給換算が最低賃金を下回らないように注意することが不可欠です。
日本では都道府県ごとに最低賃金が設定されており、これは日割り給与にも当然適用されます。途中入社や欠勤の理由を問わず、支給される金額が法定の最低賃金を下回ってはなりません。
特に、欠勤や短時間勤務が発生した場合は賃金総額が減少しますが、最低賃金レベルをクリアしているかを必ずチェックしてください。違反が発覚した場合には、企業イメージの低下や行政指導の対象となるリスクが高まります。
7. 日割り計算時の端数処理と注意点

日割り計算を行う際は、1円未満の端数や小数点以下の計算処理についてのルールを定めることが重要です。
計算途中で生じる端数を四捨五入、切り捨て、切り上げのどれにするかによって、従業員が受け取る正味額に差が出る可能性があります。どのように処理するかを就業規則で明記し、一貫性を保つことで、不公平感を与えずに済みます。
特に大人数の企業では、端数処理の基準を決めないまま放置すると、担当者ごとに計算結果が異なるリスクがあります。計算の自動化も含めて、整備を進めることが望ましいです。
8. 給与計算システムやクラウドツールを活用するメリット

複雑化しやすい給与の日割り計算を効率よく正確に実施するためには、専用の給与計算システムやクラウドツールを活用する方法があります。
自動計算機能や勤怠データの連携機能を備えたシステムを導入すると、人為的なミスが起こる可能性が格段に下がります。また、残業代や有休管理などほかの要素とも連携しやすいため、総合的な労務管理の効率化につながるでしょう。
ツール導入によって手間やコストを削減できる一方で、従業員情報のセキュリティ対策も忘れてはなりません。信頼性の高いベンダーやクラウドサービスを厳選し、定期的なシステム更新やバックアップでリスクを回避しましょう。
9. まとめ:適切な日割り計算で公正な労務管理を

給与の日割り計算は、企業が従業員の勤務実態を正しく評価し、適正な賃金を支払うための重要なプロセスです。
法的には具体的な規定がないからこそ、それぞれの企業が合理的かつ公正なルールを策定することが求められます。暦日数方式、所定労働日数方式、月平均所定労働日数方式、実労働日数方式など、いずれの計算方法を採用するにしても、従業員への丁寧な説明が欠かせません。
また、手当・控除の扱い方や最低賃金、端数処理などの詳細に至るまで就業規則で明示し、透明性を高めることがトラブル回避の鍵です。適切なシステムやツールを取り入れ、公正な給与管理を実現することで、企業と従業員双方の信頼関係を育んでいきましょう。