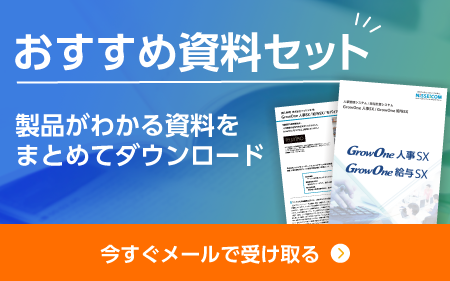休業手当とは? 法的根拠や対象範囲、計算方法をわかりやすく解説

2026年1月15日
休業手当は、企業の都合等により従業員を就業させることができず休業となった場合に、一定の補償として支払われるものです。労働基準法第26条で規定されており、事業者には平均賃金の60%以上を支払う義務があります。
一方で、事業が予期せぬトラブルに直面して休業を余儀なくされる場面や、自然災害や新型コロナウイルス感染症など外部要因による休業の扱いについては、判断に迷うことも少なくありません。
本記事では、休業手当に関する基本的な定義、法的根拠、具体的な支給対象および計算方法に至るまで、企業の実務対応を中心に分かりやすく解説します。
目次
1.2. 休業手当は賃金? 支給時の扱いについて 2.1. 業務上の負傷・疾病の場合:休業補償の概要
2.2. 使用者の責に帰すべき事由とノーワーク・ノーペイ原則 3.1. 自然災害や非常事態による休業
3.2. 新型コロナウイルスに伴う休業事例 4.1. 支給対象となる従業員と算出の基本計算式
4.2. 平均賃金の計算方法と注意点
4.3. パート・アルバイト・派遣社員への対応 5.1. 業績不振による休業と休業手当
5.2. 部品供給ストップによる休業
5.3. 従業員とのトラブル事例と解決策 6.1. 就業規則と労使協定の整備
6.2. 雇用調整助成金など公的支援制度の活用
1. 休業手当の基本定義と法律上の根拠

まずは、休業手当の定義や法律的な根拠を把握することが重要です。従業員が働けなくなった期間のうち、どのような状況が「休業」に該当し、どのように休業手当が支給されるのかを理解しておきましょう。
休業手当は労働基準法第26条に基づき、使用者の責に帰すべき理由によって従業員が休業せざるを得ない場合に支払われる賃金です。具体的には、会社都合による経営不振や設備不備などが該当し、これらが「使用者の責に帰すべき事由」として認められる場合、企業に支払い義務が発生します。
一方、自然災害のような不可抗力や、会社に全く責任がない事象では、支払い義務がない場合もあります。そのため、休業手当の支給可否を判断する際は、休業の背景が「会社都合」に当たるかどうかを慎重に見極める必要があります。
労働基準法における休業手当の計算方法は、過去3か月間の賃金総額を該当日数で割った平均賃金の60%以上を支給することが原則です。この制度により、従業員は生活保障を受けられ、企業にはリスク管理としての役割が求められます。
1.1. 休業・休暇・休日の違い
休業とは、企業側の都合などにより労働を提供できない状態を指し、労働基準法上の休業手当の対象となる可能性があります。この点において、有給休暇や法定休日とは区別されます。有給休暇は従業員の請求に基づき取得する有給の休暇であり、法定休日は法律で定められた週に1日以上の休みを指します。
休業は、労働者が働く意思と能力を持っているにもかかわらず、企業の都合により働けない場合を指すため、従業員本人の都合とは異なります。休日や休暇は、予定された休みや従業員側の事情に基づき取得するものが中心です。
それぞれ発生原因が異なるため、休業手当が適用されるかどうかは、あくまで「使用者側に休業の責任があるか」が判断基準となります。その違いを正しく理解し、誤って手当を支払わない、あるいは不要に支払ってしまうなどのミスを防ぐことが重要です。
1.2. 休業手当は賃金? 支給時の扱いについて
休業手当は法律上「賃金」として扱われます。そのため、源泉所得税や社会保険料の計算上、一般の給与支給時と同様に、保険料や税金が控除される点に留意する必要があります。
なお、業務上の負傷や疾病による休業補償は非課税となる場合があるため、この違いは実務上重要です。
また、休業手当が発生するかどうかは企業の裁量ではなく、法令により義務づけられているため、適正な支給を怠ると労働基準法違反に問われるリスクがあります。企業規模や経営状態にかかわらず、法律に基づいて対応することが求められます。
企業としては、就業規則や賃金規定に休業手当に関するルールを明文化し、従業員に周知徹底することが望ましいです。支給の有無や計算方法が不透明だと、従業員とのトラブルにつながりやすいため、明確な取り扱いルールの策定は重要です。
2. 休業手当と休業補償の違い

休業が生じた場合でも、業務上の負傷や疾病による休業補償と、休業手当は異なるものであり、法的根拠や適用範囲が違います。両者を適切に区別することで、トラブルの防止や従業員の安心につながります。
休業手当は、会社都合により従業員が働けなくなった場合に支払われます。一方、休業補償は労災保険の適用を受ける場合に支給されるものです。具体的には、業務上の事故や仕事が原因の負傷が発生した際、従業員には休業補償を受ける権利があります。
休業補償は非課税扱いとなる場合が多く、給付の財源も雇用保険ではなく、主に労災保険です。このため、税務上の取り扱いも異なり、企業が全額を負担する休業手当との区別は非常に重要です。
2.1. 業務上の負傷・疾病の場合:休業補償の概要
業務上の負傷や疾病による休業の場合、従業員は労災保険から給付を受けることができます。休業手当とは異なり、会社が独自に支給するものではなく、公的保険制度により給付される点が特徴です。
支給額は平均賃金の60%相当となり、概算計算は休業手当に類似していますが、支給の根拠が異なります。また、非課税である点も労働者にとって大きなメリットです。
ただし、どの程度が労災として認定されるかはケースごとに異なるため、労働基準監督署への申請手続や医療機関の診断書など、必要書類を揃えて正確に申請することが求められます。
2.2. 使用者の責に帰すべき事由とノーワーク・ノーペイ原則
使用者の責に帰すべき事由がある場合には休業手当が発生し、そうでない場合は原則として給与支払い義務はありません。これは「ノーワーク・ノーペイ」の原則と呼ばれ、労働が行われなかった日の賃金は支払われないという考え方に基づいています。
ただし、スムーズな生産体制を維持できなかった企業側にも一定の責任があると判断された場合には、ノーワーク・ノーペイの原則が全面的に適用されないこともあります。使用者の責任の有無については、経営判断の誤りや設備投資の遅れなどが争点となりやすいです。
結果的に、どちらの責任が重いのかを法的に判断するには、個別事情を精査する必要があります。トラブルを防ぐためにも、事前にリスク管理を行い、企業の責任が問われる事態の発生を極力回避することが重要です。
3. 休業手当が必要となるケースとは?

休業手当の支払いが必要となる主なケースは、使用者の都合による休業が発生した場合です。具体的にはどのような事態が該当するのでしょうか。ここでは、自然災害や新型コロナウイルス等、実際に発生しうる事例を確認します。
使用者に責任があるとされる代表的なケースとしては、売上不振による一時的な経費削減のための休業や、生産ラインの設備不備による休業が挙げられます。これらの場合、労働者側に落ち度がないため、労働基準法に基づき休業手当の支払い義務が生じます。
一方、自然災害や非常事態など、企業の責任を問えるか判断が難しいケースもあります。火災や台風による施設の破損があった場合でも、事前の防止策が不十分と判断されれば、使用者の責任の一部が認められる可能性がある点には注意が必要です。
3.1. 自然災害や非常事態による休業
地震や台風、洪水などの自然災害は、一般的に不可抗力に該当します。そのため、原則として企業の責任とはみなされず、休業手当の義務は発生しないとされることが多いです。
しかし、企業が重大な設備投資を怠る、あるいは防災対策をまったく講じていない場合には、裁判などで「使用者の責任を否定できない」と判断される可能性があります。
判例などでは、災害の程度や事前の対策状況などが総合的に考慮され、企業に落ち度があると認められれば、部分的に休業手当の支払い義務が生じるケースもあります。そのため、防災対策やリスクマネジメントに力を入れることが重要です。
3.2. 新型コロナウイルスに伴う休業事例
新型コロナウイルス禍では、国や自治体の要請により休業を余儀なくされた企業が多くありました。経営上の判断も重なり、企業側の責任範囲と不可抗力の線引きが注目される場面が増えています。
労働局の指針では、社会的要因により休業させる場合でも、一定の事由においては使用者側の責任が否定できないとされています。その結果、休業手当の支払い義務や、雇用調整助成金などの活用が必要になる場合もあります。
実際の例として、感染拡大防止措置の一環として一時的に店舗を閉鎖し、従業員が自宅待機を余儀なくされたケースなどが挙げられます。このような場合、適切な休業手当の計算と支給を行わないと労使トラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
4. 休業手当の支給対象と計算方法

誰に、どの程度の金額を支払うのかは、実務上の最重要ポイントです。支給対象の範囲や計算方法を正確に理解し、法令違反を防ぐとともに、従業員の生活保障を適切に行うことが大切です。
支給対象は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員など、さまざまな雇用形態に及びます。雇用形態により労働条件に違いがあっても、「会社都合で休まざるを得なくなった」という事実があれば、休業手当が発生する可能性がある点に注意しましょう。
計算方法の大まかな流れとしては、まず直近3か月間の賃金総額から1日あたりの平均賃金を算出し、その60%以上を支給する必要があります。対象となる賃金には、基本給だけでなく、各種手当や残業代などが含まれる場合が多いため、正確な算出には従業員一人ひとりの実績を把握することが重要です。
4.1. 支給対象となる従業員と算出の基本計算式
休業手当の支給対象は「使用者の都合で労働を提供できなかった従業員全員」です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員なども含まれます。ただし、内定者や日雇い労働者については、雇用契約の開始時期や形態によって支給対象外となるケースもあるため、契約内容の確認が重要です。
基本的な計算式は「平均賃金×60%以上」であり、平均賃金は過去3か月間の賃金総額を総日数で割って算出するのが一般的です。この平均賃金には、基本給だけでなく、諸手当や残業代が含まれる場合が多いため、正確な賃金データの管理が求められます。
なお、「平均賃金×60%」は最低限の基準であり、企業によっては従業員の生活を考慮して100%支給している場合もあります。支払割合の設定は企業ごとの判断ですが、法定の基準を下回ることはできません。
4.2. 平均賃金の計算方法と注意点
平均賃金を算出する際は、単純に月給だけで計算するのではなく、ボーナスや特別手当、残業代などの変動要素の取り扱いを明確にしておく必要があります。通勤手当など支給条件が明確な額は、賃金総額に含まれない場合もあるため、就業規則や給与規定のルールを確認しましょう。
また、過去3か月間に産休や育児休業などの長期休暇が含まれている場合、平均賃金の計算期間から除外できるルールが存在しています。計算ミスを防ぐためにも、個別ケースを整理し、適切に按分することが重要です。
最終的には、適正な平均賃金を基に休業手当の総額を算出して支給することで、従業員に法令通りの補償を行うことができます。こうした計算手続きや書類管理は、可能な限りシステム化することで、誤算やトラブルを回避しやすくなります。
4.3. パート・アルバイト・派遣社員への対応
非正規雇用の従業員も休業手当の支給対象となるため、雇用形態ごとに明確な基準を定めることが重要です。特に派遣労働者の場合、派遣元と派遣先のどちらが休業手当を負担するかについては、トラブルが発生しやすいので注意が必要です。
一般的には、雇用契約が存在する派遣元が休業手当の支払い義務を負うとされています。しかし、派遣先の都合によって休業が発生する場合には、派遣元と派遣先がどのように費用を分担するかについて協議することが望ましいでしょう。
さらに、パートタイムやアルバイトも家庭の生計を支える重要な働き手である場合が多いため、休業手当の支給については正社員と同様の手続きを取ることが求められます。企業として、不公平感やモラルダウンを防ぎ、適切に支給を行うことが重要です。
5. 具体的な休業手当の事例

企業の経営状態や外部要因により休業に踏み切るケースは多様に存在します。それに付随する休業手当について、事例を通して理解を深めていきましょう。
休業に至るにはさまざまな事情がありますが、最終的に休業手当が支払われるかどうかは「使用者の責任がどの程度認められるか」に左右されます。ここでは主に経営不振、外部サプライヤーのトラブル、従業員との紛争の事例に焦点を当てて解説します。
トラブルを未然に防ぐためには、就業規則の明確化や十分な説明責任、そして労使間のコミュニケーションが不可欠です。
5.1. 業績不振による休業と休業手当
景気の悪化や取引先の縮小などにより、売上が急激に減少し、経営が厳しくなって一時的に工場や店舗を休止するケースがあります。このような場合、従業員に責任はないため、法律上は企業が休業手当の支払い義務を負うことになります。
導入策としては、雇用調整助成金などの公的支援制度を活用し、従業員の生活を守りつつ、会社のコストを抑えることが一般的です。適正な要件を満たせば一部助成が受けられるため、休業手当の支払原資の確保に大きく寄与します。
業績回復が見込まれる場合は、安易に解雇を検討する前に休業手当を活用し、雇用維持の施策を講じることも有効です。従業員のモチベーションや企業の社会的信用を高めるためにも、十分に検討すべき選択肢といえます。
5.2. 部品供給ストップによる休業
海外のサプライヤーによる部品供給の停止や物流状況の悪化などの影響により、生産ラインが停止することがあります。これらは企業にとって不可抗力となる場合が多いですが、対策が不十分であれば使用者の責任が問われることもあります。
リスク管理の観点では、部品の在庫を一定水準で確保したり、複数の仕入先と契約したりするなど、事前に対策を講じておくことが一般的です。これらの対策を行っていたかどうかが、休業手当の支払い可否をめぐる争点となる可能性があります。
サプライチェーンの途絶が長期化した場合、雇用継続とコスト削減のバランスをどのように図るかが、企業にとって重要な課題となります。企業は、被害を最小限に抑えるための対応策をあらかじめ整備しておくことが求められます。
5.3. 従業員とのトラブル事例と解決策
休業手当の支給額や支払時期、対象範囲が不明確であると、従業員との間で紛争が生じやすくなります。特に、計算根拠が明示されないまま減額されたり、支給自体が行われなかったりした場合は、労働基準監督署へ通報される可能性もあります。
解決策としては、就業規則や労使協定に休業手当に関するルールを具体的に定め、従業員に十分説明することが重要です。従業員の理解が得られれば、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
また、万が一紛争に発展した際は、第三者機関や労働委員会による調停制度を利用する方法もありますが、企業が事前に丁寧な対応を行うことで、大きな問題に発展するリスクを避けやすくなります。
6. 休業手当をめぐる企業の実務対応ポイント

休業手当を適切に運用するためには、規則の策定と公的支援制度の活用が不可欠です。従業員の生活を守りつつ企業リスクを回避するためにも、実務のポイントを確実に把握しましょう。
まず、就業規則や賃金規定には、休業手当に関する詳細な取り扱い方法を明文化しておくことが重要です。法令で定められている内容を踏まえ、さらに企業独自の規定を設ける場合は、労働組合や従業員代表の意見を考慮し、公平かつ具体的なルールを策定することが求められます。
また、雇用調整助成金などの公的支援制度について情報収集を継続的に行い、要件を満たす場合は積極的に活用しましょう。助成金申請には書類準備や手続きが必要ですが、休業手当の財源確保につながるため、企業経営上の大きなメリットとなります。
さらに、従業員に対して休業手当の仕組みや支給のタイミングを丁寧に説明し、不明点が生じた場合は、相談しやすい窓口を設置することも重要です。こうした取り組みが労使間の信頼関係を高め、職場の安定や企業の信用力向上につながります。
6.1. 就業規則と労使協定の整備
休業手当に関する規定を就業規則に整備する際は、労使間協定として明記することが望ましいです。就業規則だけでなく、労働組合や従業員代表との協定で詳細なルールを定めておくことで、実際に休業が発生した場合の混乱を防げます。
特に、支給割合の算定根拠や算定期間、支給されるタイミング等を明確にしておくことで、従業員からの信頼を得やすく、紛争回避にも効果的です。
条文の解釈が曖昧なままだと、企業と従業員の認識の食い違いが顕在化する可能性があるため、早い段階でルールを制定しておくことをおすすめします。
6.2. 雇用調整助成金など公的支援制度の活用
休業手当の支払いは、企業にとって大きな負担となる場合がありますが、雇用調整助成金などの公的支援制度を適切に活用することで、財政的な負担を軽減できる可能性があります。
新型コロナウイルスの拡大期には、助成率や上限額が引き上げられた制度もあり、多くの企業が救済を受けました。ただし、申請には締め切りや細かな要件があるため、最新情報を常に確認しておくことが重要です。
公的支援を利用する際は、必要書類の整備や休業実績の管理が必須となり、不備があると受給できなくなる場合があります。事前の準備と正確な手続きを行い、経営リスクを適切に管理しましょう。
7. まとめ・総括

休業手当は、企業と従業員の双方にとって重要な制度であり、法的リスクを回避しつつ、公平かつ適正に運用することが求められます。
企業側から見ると、経営状況の変化や外部要因による休業リスクは避けられませんが、労働者保護の観点から休業手当を適切に支給する義務があります。特に、労働基準法第26条の枠組みや、助成金などの公的支援を効果的に活用することで、従業員の生活保障と企業のコスト対策を両立することが可能です。
重要なのは、休業が発生する前段階から就業規則や労使協定を整備し、社内外のリスクを分析しておくことです。正確な計算と適切な手続きを行うことで、従業員とのトラブルを回避し、円滑に休業期間を乗り切ることができます。
最終的には、企業のコンプライアンスと従業員の安心を確保するためにも、休業手当に関する知識と運用方法をしっかり理解しておくことが不可欠です。今後も法改正や社会情勢の変化に注意を払い、適切な情報収集と柔軟な対策を継続していきましょう。