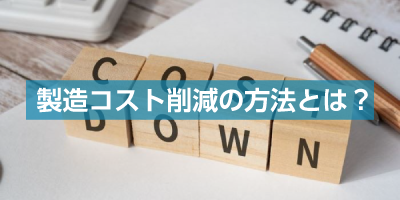【製造業の利益率】平均の目安から改善策まで徹底解説

製造業は多種多様な製品を扱い、市場規模も大きいため、利益率の動向は企業の経営判断を左右する重要な指標です。一般的な目安として、営業利益率が5%から10%であれば優良、10%を超えれば超優良とされることがあり、業界としては4%前後が平均とされています。
本記事では、製造業における利益率の基本的な考え方から平均的な数値、業種別の特徴、具体的な改善ポイントに至るまでを分かりやすく解説します。
目次
(2)衣服・繊維製品製造業
(3)自動車・機械製造業
(4)化学・プラスチック製品製造業
(5)金属製品製造業 (1)売上高総利益率(粗利益率)
(2)売上高営業利益率
(3)売上高経常利益率
(4)自己資本経常利益率(ROE)
(5)総資産利益率(ROA) 要因1:生産性の低下や業務効率の悪化
要因2:原材料費や人件費などのコスト増加
要因3:売上高と原価の適切な管理不足 ポイント1:コスト削減策の徹底
ポイント2:業務効率化とDXの活用
ポイント3:製品価値向上と価格戦略の見直し
ポイント4:販売チャネルの再検討と新規開拓
1. 製造業の利益率とは?基本概念と重要性

製造業の利益率は、製品を作る際にかかったコストと販売による収益のバランスを示す重要な指標です。
利益率とは、売上に対してどの程度の利益が残るかを示す割合のことです。製造業の場合、原材料コストや人件費、設備投資などが大きく影響するため、利益率を正しく把握することが経営判断の基盤となります。
特に製造業では、製造プロセスごとにコスト構造が異なることが多く、効率的な生産体制や価格戦略によって利益率が大きく変動します。逆に、問題点を放置したまま生産を続けると赤字に陥るリスクも高まります。このように利益率の管理は、単なる数字の把握だけでなく、事業の継続性や成長戦略を考える上でも欠かせません。
合理的なコスト削減や適切な価格設定などの施策を講じるためには、まずは利益率の本質を正しく理解することが求められます。
2. 【業種別】製造業の利益率比較

製造業全体の平均を超えて、さらに業種ごとの特徴を押さえることで、利益率の違いがより明確になります。
同じ製造業でも、扱う製品やビジネスモデルによってコスト構造や売上形態が大きく異なります。例えば、消費財をメインに取り扱う企業では在庫リスクが高まる一方、高付加価値の工業製品を扱う企業では研究開発や設備投資が利益に影響を与えます。
業種別の特徴を理解することは、市場での競合状況や顧客ニーズを的確に捉えるためにも重要です。自社に合った戦略を立案して利益率を向上させるためには、まず自社が属する業種の特性をしっかり把握しましょう。
以下で、代表的な製造業の業種別に注意すべきポイントや平均的な利益率動向について見ていきます。
(1)食料品製造業
食料品製造業は、原材料コストの変動や賞味期限の管理など、利益率を左右する要素が多い業種です。安定した需要がある一方で、天候不順による原材料の高騰や流通コストの増加に悩まされることも珍しくありません。
価格転嫁が難しい場合もあるため、効率よく生産から販売までを行うことが、利益を左右します。また、設備投資の負担や品質管理に伴うコストも大きく、常にコスト構造を見直す姿勢が求められます。
一方で、健康志向や高付加価値商品の展開などで新たな需要を取り込めれば、利益率が向上する可能性もあります。徹底した市場調査と継続的な設備投資とのバランスがカギとなります。
(2)衣服・繊維製品製造業
ファッション性や流行に大きく左右されるのが、衣服・繊維製品製造業です。シーズンごとのトレンドを的確に捉えないと、在庫過多が発生し、価格の値下げや廃棄といったコストにつながります。
また、原材料費のほかに縫製などの人件費が大きな割合を占めることも特徴であり、特に海外の生産拠点を持つ企業は、為替リスクや国際情勢の変化に敏感になる必要があります。
流行に応じた短期的な対応能力と在庫管理の徹底、そしてブランド価値の維持が利益率を左右するポイントとなります。
(3)自動車・機械製造業
自動車や機械製造の業界では、大量生産と高品質を同時に求められます。研究開発費や設備投資額が非常に大きく、長期的な投資回収を見込んだ経営が求められます。
一方、海外への販路拡大や精密エンジニアリング技術による差別化を通じて、高い利益率を達成している企業も存在します。安全性や信頼性の向上を追求し続ける姿勢が重要です。
さらに、環境規制や電動化のトレンドなど、世界的な潮流も無視できません。時代の変化に適応することで、将来的にも安定した利益を生み出せる基盤を築くことが可能です。
(4)化学・プラスチック製品製造業
化学・プラスチック製品の分野は、原材料の価格変動や環境規制への対応が利益率に直接影響を及ぼします。石油価格の変動や国際的な規制強化など、政治・経済情勢に左右される要素が大きいです。
また、製品自体が産業の基盤を支える素材であるため、景気の波や他業界からの需要により受注量が大きく変動する可能性もあります。環境負荷を低減する新素材の開発や、高機能製品の研究開発に成功すれば、高付加価値を創出し、利益率を高める機会が生まれます。
(5)金属製品製造業
金属製品製造業は、鉄鋼などの原材料価格の動向に大きく左右されやすい分野です。世界的な需要の増減や関税政策、資源保護政策が価格に大きな影響を与えるため、経営者は中長期的なリスクを考慮した原材料調達を行う必要があります。
また、設備投資として大規模な工場や加工ラインを保有する企業が多く、メンテナンス費用や減価償却費が利益を圧迫する要因にもなります。国内外の需要動向を注視しながら、生産効率を高める工夫が求められます。付加価値の高い精密加工技術を磨き、差別化を図ることが利益率向上の鍵となります。
3. 製造業における各種利益率の種類と計算方法
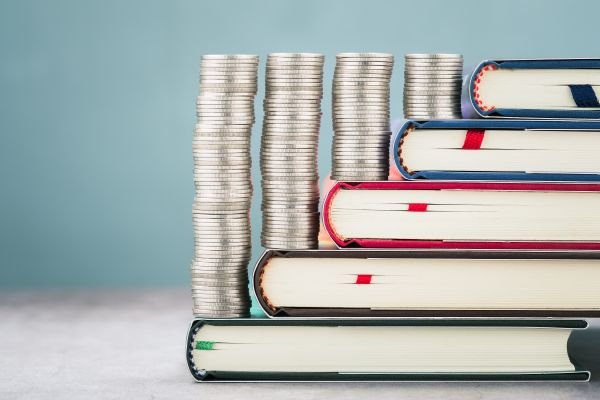
一口に利益率といっても、複数の指標があり、それぞれが異なる側面から企業の収益力を評価します。
製造業では、売上とコストの関係をさまざまな角度で把握するために、いくつもの利益率指標が用いられます。例えば、粗利益率は製造原価との比較に焦点を当てるのに対し、営業利益率はコアビジネスの収益力に注目します。
経常利益率は金融収支や投資状況も含めた通常の営業活動全体を反映し、ROEやROAのような指標は資本や資産の効率的な活用度合いを示します。これらを総合的に評価し、自社の課題を見極めることが重要です。
ここからは、代表的な利益率指標とその特徴、計算方法を確認していきます。
(1)売上高総利益率(粗利益率)
売上高総利益率は、売上高から製造原価を差し引いた粗利益を売上高で割って算出する指標です。
つまり、製品製造の変動費を差し引いた後に、どれだけ利益が残るかを示します。この指標が高いほど、製品の付加価値が大きいか、原材料費や直接人件費を抑制できている可能性があります。ただし、固定費や販売管理費を含まないため、それらのコストを考慮する必要があります。
製品の原価構造を見直す際や付加価値アップを狙った商品開発を検討する際に、特に注目される利益率です。
(2)売上高営業利益率
売上高営業利益率は、売上高に対するコア事業の利益割合を示します。
販売管理費なども差し引かれるため、製造現場だけでなく、営業やマーケティング活動の効率にも大きく影響します。一般的に5%から10%を優良の目安とする企業が多く、これを安定して維持できれば、ビジネスモデルが着実に機能していると評価できます。
また、コスト削減や価格戦略の見直しによって短期的な改善も期待できる指標のため、経営陣が日々注目する数値の一つです。
(3)売上高経常利益率
経常利益率は、本業に加え、営業外収益や営業外費用を含め、通常の営業活動全体を反映する指標です。
資金調達コストや投資利益も組み込まれるため、企業の総合的な経営力を示す数字といえます。自社の投資判断やキャッシュフロー管理に大きく影響し、経常利益が安定して高い企業は金融機関からの信用も得やすくなります。逆に大きく変動しやすい場合は、経営リスクへの対応力を強化する必要があります。
業界平均と比較する際には、資金調達の仕組みや金融収益の規模を把握すると、より正確な評価ができます。
(4)自己資本経常利益率(ROE)
ROEは、株主資本に対してどれだけ効率よく利益を生み出しているかを示す指標であり、投資家が企業価値を判断する際に最も重視する指標の一つです。
特に製造業では大きな設備投資を伴うことが多いため、資本構成や負債とのバランスをしっかりと考えなければ、十分なリターンを得ることが難しくなります。また、ROEが高くても短期的な投資回収に依存しているケースもあるため、持続的に成長できるビジネスモデルであるかを見極めることが重要です。
(5)総資産利益率(ROA)
ROAは、総資産に対してどの程度の利益を創出しているかを示す指標で、経営資源をどれだけ有効に活用しているかを知る手がかりとなります。
製造業では、工場や機械装置などに多額の資本が固定化されやすいため、ROAが低くなりがちです。ただし、生産効率の高いラインを構築できれば、収益性も大きく向上します。総資産をどのように活用して新しい価値を創出するかは、デジタル化や設備改善といった施策によって大きな差が生じることがあります。
4. 利益率が低下する要因とは?

製造業で思うように利益率が伸びないのは、複数の要因が絡み合っているケースが多いからです。利益率が低下している背景には、生産の非効率化や原材料費の高騰など、さまざまな要因があります。特に、海外からの原材料調達に依存している企業や、技術者不足の人材問題を抱えている企業は注意が必要です。
また、価格交渉力の弱さや需給変動が激しい分野では、売上高が大きくても収益性を確保しづらいことがあります。これらの要因を的確に分析し、早期に原因を特定することが、利益率改善の第一歩です。
ここでは、代表的な原因を三つ挙げ、それぞれの対策を考えます。
要因1:生産性の低下や業務効率の悪化
生産ラインの不適切な配置で作業動線が長くなったり、機械の稼働率が低く遊休設備が多くなったりした場合、早急な改善が求められます。作業標準の未整備や人材育成の遅れにより、同じ作業でも生産品質と時間にばらつきが生じると、無駄なコストの増加につながります。
さらに、紙ベースの管理や属人的なノウハウに依存すると、業務効率が大幅に低下するリスクもあります。デジタルツールを活用し、作業効率の可視化と改善を図ることが重要です。
要因2:原材料費や人件費などのコスト増加
国際情勢や為替の変動により、原材料費や人件費が予想外に高騰することがあります。長期的な取引契約の締結や価格ヘッジを活用することで、投機的なコスト増加を抑えることが求められます。
人件費は企業のコスト構造に直結するため、慢性的な人手不足や熟練工の退職などが発生すると、さらにコストが増大するリスクがあります。自動化や省力化を図ることで労務費の削減も行い、同時に変動に対応可能な雇用形態の見直しが必要です。
要因3:売上高と原価の適切な管理不足
利益率を維持するには、販売価格と製造原価のバランスを常に見直すことが重要です。販売価格が低すぎると、売上高が増えても利益が伴わず、逆に価格を高くすると市場競争力を失う恐れがあります。
また、在庫管理や受注予測が不十分であると、過剰在庫による保管コストの増加や値引き販売などが発生し、利益率に影響するダメージを与えます。営業部、生産部、経理部など部門を横断して情報を共有し、需要と供給のバランスを常に監視することが必要です。
5. 製造業の利益率を改善するためのポイント

利益率は、売上高の拡大と同時にコストの最適化を図ることで、総合的に向上させることができます。製造業における利益率を高めるためには、余分なコストを削減しつつ、売上の効率的な拡大を図る戦略が重要です。そのために、コスト構造を可視化し、そして生産プロセスや管理業務を徹底的に効率化するアプローチが効果的とされています。
また、高付加価値の商品開発や新しい販路の拡大など、売上を伸ばす取り組みも重要です。価格戦略を再考し、ブランドイメージを確立して顧客が求める価値を提供することにより、適正な販売価格を設定しやすくなります。
以下のポイントを踏まえて、コストの面だけでなく、付加価値や販売戦略も含めた総合的な経営改善を目指しましょう。
ポイント1:コスト削減策の徹底
原材料の購買ルートを見直して、より安定的かつ費用を抑えられるサプライヤーとの取引を模索するなど、仕入れコストの圧縮が有効です。
間接費や固定費の分析を行い、不要な支出を洗い出すことも欠かせません。事務作業の外注化や生産ラインのところどころで使用される小資材の費用削減も効果を発揮します。設備投資については、短期的な支出だけでなく、長期的なリターンを見据え、投資対効果を常に評価しながら進めると無駄なコストを抑えやすくなります。
ポイント2:業務効率化とDXの活用
生産管理システムやIoT、AIなどの技術を導入することで、リアルタイムに製造工程や在庫状況を把握し、ボトルネックを迅速に発見し是正することが可能です。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、従来の紙や人手に頼る業務フローを自動化し、スタッフが付加価値の高い業務に集中できる環境を整備します。業務改革には現場の協力と共通の目標設定が必要不可欠です。導入前には教育や運用ルールの整備を行い、スムーズな定着を目指した計画を策定しましょう。
ポイント3:製品価値向上と価格戦略の見直し
単に価格の安さで差別化を図ることは、競争の激しい市場では限界があります。製品に独自性や高品質を付加することで、価格に応じた価値を顧客に提供できるようになります。
コスト削減に過度に注力すると、品質の低下やブランドイメージの毀損を招く可能性があるため、バランスを取りながら価値向上を目指します。既存の商品ラインナップを再評価し、投資すべき製品と削減すべき部分を判断し、戦略的にリソースを配分しましょう。
ポイント4:販売チャネルの再検討と新規開拓
オンライン販売や海外市場への進出など、新たな販路を開拓することで、顧客層を拡大し、売上の拡大とリスク分散を同時に狙うことができます。販売代理店や提携パートナーとの協業も有効な手段です。販路の見直しを通じて、固定費を抑えながら効率的に販促活動を行うことが可能です。
新しいチャネルを開拓する際には、マーケット調査を綿密に行い、文化や消費者の嗜好を正しく理解した上で製品やサービスを調整することが重要です。
6. 利益率向上に成功した製造業の事例

実際に利益率改善に成功した企業の具体例は、自社が取るべき次の行動をイメージするうえで大きなヒントになります。
ある中小の金属部品メーカーでは、コンサルティングを受けて生産ラインを全面的に再編し、機械稼働率を向上させることに成功しました。それまで分散していた在庫管理や購買データを統合的に管理し、原材料の無駄を削減することで営業利益率が数ポイント向上したといいます。
また、DX化を積極的に進めた食品加工メーカーの例では、温度管理や設備保守のタイミングをデジタルで一元化し、ロスを最小限に抑えました。リアルタイムでの在庫確認や需要予測により、製造計画を柔軟に調整し、業務効率化と製品クオリティの向上を同時に実現しています。
これらの事例に共通するのは、部分的な改善ではなく経営全体を戦略的に見直した点です。コスト構造や生産プロセス、販売チャネルまでを含めて統合的に取り組むことで、利益率を大幅に向上させることが可能になりました。
7. まとめ・総括

製造業における利益率向上を実現するためには、現状把握から戦略立案、具体的な行動管理まで一貫して行うことが必要です。
まずは、業界平均や他社の動向と比較し、自社の利益率を正しく把握することが重要です。それには、売上高総利益率、営業利益率、経常利益率、ROE、ROAなど複数の指標をバランスよくチェックする必要があります。利益率低下の要因を分析し、生産ラインの改善やコスト削減、価格戦略の最適化といった具体策を継続的に実行することがポイントです。
さらに、オンラインや海外市場への参入など、新しい販路の開拓も欠かせません。経営改善には短期的な施策だけでなく、長期的な視点での投資や組織改革を含めた総合的なアプローチが必要です。将来を見据えた取り組みによって安定した利益率と持続的な成長を同時に実現していきましょう。