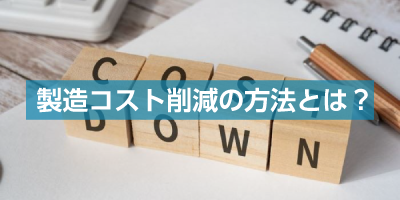暗黙知と形式知がカギ! 製造業の技術伝承・知識共有を加速する

製造業において高い技術力を維持し続けるためには、ベテラン職人のノウハウから若手エンジニアが学ぶ仕組みを築くことが欠かせません。
本記事では、暗黙知と形式知の特徴を理解した上で、具体的なナレッジマネジメントの手法やSECIモデルの実践ポイントを解説します。技術が属人化しがちな製造業で、どのように知識を共有しイノベーションを生み出すか、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.2. 造業における暗黙知の具体例 2.1. 形式知の定義と特徴
2.2. 製造業における形式知の具体例 4.1. 属人化の防止と組織力の強化
4.2. 人材育成・教育コストの削減(技術伝承)
4.3. 企業成長とイノベーション促進 5.1. 人材の教育に時間がかかる
5.2. スキルが属人化して代替が難しい
5.3. メンバーのスキル管理が不透明になる 6.1. 業務フローの可視化と知識の抽出
6.2. 情報共有しやすい仕組みづくり 7.1. 暗黙知を形式知化するプロセスの全体像
7.2. ナレッジ・リーダーシップによる知識ビジョンの策定 ステップ1:共同化(Socialization)でノウハウを共有
ステップ2:表出化(Externalization)で知識を言語化する
ステップ3:連結化(Combination)で情報を整理・統合
ステップ4:内面化(Internalization)で組織知を個人が活用
SECIモデルを促進する4つの「場(ba)」のデザイン 9.1. ドキュメント管理と動画・SNSによる知識共有
9.2. AIやクラウド活用で形式知化を効率化 11.1. 知識の保護と権限設定の重要性
11.2. 難度スキルへのアプローチと継承方法
1. 暗黙知とは何か

暗黙知は、経験や勘、職人技など個人の頭の中に蓄積され、言語化が難しい知識を指します。
暗黙知は、その人の長年の経験や現場での試行錯誤から得られるため、具体的な数値やトレーニングマニュアルに落とし込むのが難しい特徴があります。表に出てこない要素が多く、属人化しやすいため、組織全体で共有されないままになることがあります。また、本人でさえ無意識に行っている部分があるので、言語化しようとしても全体像を捉えるのに苦労することがあります。
しかし、この暗黙知こそが、競合他社には真似できない製造業の強みを生み出す源泉です。長い年月をかけて培われた技術やセンスは、単に知っているというだけではなく、実践を繰り返して初めて自分のものになります。これにより、暗黙知の共有が進めば、人材が幅広く活躍する土台ができ、技術の習熟度も加速度的に上がります。
暗黙知を意識的に掘り起こし、組織が資産として活用できる状態を作ることは、今後の製造業にとって非常に重要です。熟練者の退職などによりノウハウが失われる前に、暗黙知の可視化や技術継承の仕組みを確立し、組織力を強化することが求められています。
1.1. 暗黙知の定義と特徴
暗黙知とは、個々人の経験に基づいた主観的な知識であり、言語や文字での説明が難しい性質を持っています。例えば、職人の指先の細かい感覚や、優れた営業担当者のタイミングの取り方などは、文章に書き起こそうとしても完全に伝えることは困難です。このような暗黙知は多くの場合、個人の中で無意識に働き、意識的な整理や記録が不十分なまま普段の業務の中で使用されています。
1.2. 製造業における暗黙知の具体例
製造業では、職人の勘や長年の経験による「ゴールデンルール」のようなものが、暗黙知の代表例です。工作機械の微調整方法や溶接の火加減、品質を左右する微妙な力加減などは、口頭で説明しきれない部分が多いと言えるでしょう。こうした暗黙知があることで、製品の品質や生産効率に影響を与えることが多く、職人がいないと再現が難しい工程が生じることもあります。
2. 形式知とは何か

形式知は会議資料やマニュアルなど、文章や図表を用いて共有可能になった知識です。
形式知は組織内で客観化・文書化されているため、誰でもアクセス可能であり、再現性が高い点が特徴です。説明書や作業手順、データ分析レポートなど、具体的な形で保管できる知識が含まれます。暗黙知に比べて共有が容易であり、操作ミスを減らせますが、作成や更新にはコストと手間がかかる面もあります。
しかし、形式知は非常に価値があり、組織全体が同じ情報をベースに業務を進めることで、品質のばらつきや不必要なやり直しを減少させることができます。さらに、標準化された知識があることで、新人社員や異動してきたメンバーでも一定水準の業務を遂行できるようになり、技術伝承の一助となるでしょう。
ただし、形式知は常に最新状態を維持することが重要です。製造工程や使用材料の変更があっても、マニュアルが古いまま放置されると、現場とのギャップが生じ、さらに属人化を招く恐れがあります。定期的に見直しと更新を行う仕組みが非常に重要です。
2.1. 形式知の定義と特徴
形式知とは、書類やデータとして表現され、第三者に伝えやすい形に整備された知識を指します。主観的な感覚を除外し、客観的に検証可能となるため、情報共有の土台として有用です。定量的な評価もしやすく、標準化やマニュアル化が進めやすいというメリットがある一方、個人の経験に基づく工夫やコツを完全に盛り込むことは難しい場合もあります。
2.2. 製造業における形式知の具体例
例として、設備の操作マニュアル、点検チェックリスト、品質基準をまとめた標準書などが挙げられます。例えば、金属加工の工程表や安全対策マニュアルは、誰が見ても同じ手順を理解できるようなドキュメントであり、作業品質の安定に貢献します。このように形式知が充実している現場ほど、新人教育や業務の引き継ぎがスムーズに進む傾向があります。
3. 暗黙知と形式知の違い

暗黙知と形式知はどちらも企業の知的財産ですが、性質や共有方法が大きく異なります。
暗黙知は、個々の経験や熟練度に深く結びついており、本人の感覚的理解を第三者に正確に伝えるのは難しい知識です。一方、形式知は情報化されて第三者が利用しやすい形に整えられています。したがって、組織全体で同じ知識基盤を持つためには、暗黙知を形式知へ変換し、誰もが扱える状態にしておく必要があります。
企業が大きくなるほど部署間のコミュニケーションや人の入れ替わりが増え、暗黙知のままだと知識が断片化するリスクが高まります。逆に、形式知が多いと一定水準の業務を保てる半面、独自の強みである暗黙知が十分に活かされないこともあります。両者をバランスよく管理・活用することが企業の競争力を維持する鍵となるのです。
このように、暗黙知と形式知は互いを補完し合う関係ですが、暗黙知を形式知に変換するには、意識的な作業やナレッジマネジメントを推進する文化が重要になります。そのプロセスを体系的に示すのがSECIモデルであり、製造業における技術伝承の基盤ともいえるのです。
4. 暗黙知を形式知化するメリット

暗黙知を形式知化することで、企業全体の生産性や競争力が飛躍的に高まります。
暗黙知を組織全体に浸透させることで、熟練者の技やノウハウがより多くのメンバーに共有されます。その結果、個々の知識の質が高まり、業務効率が向上すると同時に、新たな改善アイデアやイノベーションが生まれやすくなります。
特定のベテラン社員しか行えなかった作業を、匿名化された知識として誰でも扱えるようにすることにより、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。また、形式知として整備されたノウハウは、時間が経過しても再利用が容易であり、組織全体のレベルアップを継続的に支えます。
加えて、技術が開示されることで、部署間の連携もスムーズになりやすくなります。販売やマーケティングからのフィードバックと製造技術が結びつきやすくなり、顧客ニーズに即した改良や新製品開発もしやすくなります。
4.1. 属人化の防止と組織力の強化
暗黙知を形式知に変換することで、ノウハウが特定の人に偏るリスクを低減できます。複数のメンバーが同じ工程を担当できるようになれば、急な離職や休職時のリスクが小さくなるだけでなく、チーム全体のスキルレベルを向上させることも可能になります。このように属人化を防ぐことは、組織の耐久力を高める重要な施策といえるでしょう。
4.2. 人材育成・教育コストの削減(技術伝承)
暗黙知が形式知として整理されていると、新人や異動者にノウハウを効率よく伝えることができます。ベテラン社員が個別に教える負担が減り、研修にかかる時間やコストを削減できるという大きなメリットがあります。また、標準化された学習プログラムを整備しておけば、社内の教育レベルが一定以上に保たれるため、全体的な生産性の向上につながります。
4.3. 企業成長とイノベーション促進
暗黙知を共有することで、知識の連携や新しいアイデアの閃きが生まれやすくなります。個人の頭の中にしかなかった技術的ヒントが、他の部署や専門分野と組み合わさることで、新製品や新サービスの開発が加速される可能性があります。結果的に、企業の成長と競争力強化に寄与し、業界での優位性を向上させることにつながります。
5. 暗黙知を形式知化できないことによる課題

暗黙知が共有されないままでいると、組織全体でさまざまな問題が生じる恐れがあります。
暗黙知がうまく共有されず、属人化が続くと、人材が不足したときや退職者が出たときに業務が立ち行かなくなるリスクが高まります。組織として柔軟に動けず、対応力が落ち、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。さらに、教育に時間や手間がかかることでコスト増にもつながります。熟練者と新任者が一対一で長期間にわたってOJTを行う場合、担当者のモチベーションや作業効率に影響が出ることが多いでしょう。
特に忙しい現場では、暗黙知を言語化してマニュアル化することの重要性を痛感するケースが多くなります。組織全体のスキル構成や業務フローが見えづらいことで、戦略的な人材配置や業務改善の施策も打ちにくくなります。どの部署にどのスキルが不足しているのかがわからないと、新製品の開発体制や品質向上に向けた動きも限られてしまい、競争力を維持するのが難しくなるのです。
5.1. 人材の教育に時間がかかる
暗黙知が中心の職場では、後進が技術を習得するために熟練者の直接指導に頼りがちです。それ自体には効果的な側面もありますが、熟練者が全員分の教育を担当するのには限界があり、育成ペースが遅れると重要な仕事がまわらなくなる可能性もあります。抜本的な対策としては、ノウハウを文章や動画にまとめるなどして形式知化することが必要不可欠です。
5.2. スキルが属人化して代替が難しい
特定の熟練技術者しか行えない作業が多い企業ほど、その人が休職や退職した場合の影響は甚大です。生産ラインの効率が急激に落ちたり、品質が安定しなくなったりするリスクが高まり、顧客や取引先からの信頼を失う恐れがあります。暗黙知を共有し、組織全体でカバーする体制を早急に整備することが、長期的な企業存続のためにも重要です。
5.3. メンバーのスキル管理が不透明になる
暗黙知が散在していると、誰がどの工程や作業を得意としているのかを把握しづらくなります。実際には複数の隠れたエキスパートがいるかもしれませんが、管理者側には見えていないため、適材適所の配置や新プロジェクトへの人選が円滑に進まない状況に陥る可能性があります。
6. 暗黙知を形式知化するための下準備

暗黙知を効果的に形式知に変えるためには、必要な基盤作りが重要です。
現場での仕事の流れを可視化し、その中でどの部分に熟練のノウハウが潜んでいるかを明らかにするステップが大切です。これを怠ると、形式知を整備しても肝心な技術が失われる可能性があります。また、情報共有の文化を社内に根づかせることも必要です。優れたシステムやツールを導入しても、部署間の連携が少なく、情報をオープンに交換しない風土では、ナレッジの活用は進みません。
一方で、従業員同士が常にコミュニケーションを取れる環境が整っていると、日々の雑談から新しい知見が生まれ、現場でのトラブル解決策が共有されやすくなります。これらは暗黙知の形式知化の前段階として不可欠な要素です。
6.1. 業務フローの可視化と知識の抽出
まずは、現場での業務手順を詳細に分析し、各フェーズで熟練者がどのように独自の判断を下しているかを把握することが重要です。作業工程をプロセスマップに変換したり、インタビューや現場観察を通じて専門家の思考プロセスを明確にすることで、暗黙知を引き出しやすくなります。このような詳細な情報が得られれば、形式知としてまとめる際に不備を防ぐことができるでしょう。
6.2. 情報共有しやすい仕組みづくり
社内コミュニケーションツールやオンライン会議システムを積極的に活用し、日常的に情報を共有する文化を醸成することが重要です。また、部署ごとにワーキンググループを作り、定期的にレビュー会や勉強会を実施することで、新たな知見や改善アイデアが集まりやすくなります。このような仕組みがあれば、暗黙知を形式知化するハードルが低くなり、成果が定着しやすくなるでしょう。
7. ナレッジマネジメントの基礎と必要性

組織のナレッジを管理・活用するための基本的な考え方とその重要性を解説します。
ナレッジマネジメントとは、企業が保有する知識を整理し、適切に共有・活用することで、業務効率やイノベーション創出を高める手法です。製造業の現場においては、暗黙知と形式知のギャップを埋め、技術伝承を円滑にするための枠組みとして有効に機能します。
基本的な流れは、知識の抽出、整理、蓄積、そして活用に分けられます。特に、日々の業務で生まれる小さな改善や学びを見逃さずに記録し、それを共有するプロセスが大切です。暗黙知を形式知として組織全体に行き渡らせるためには、この一連の流れを継続的に回す仕組みを設計する必要があります。
また、ナレッジマネジメントには、トップやリーダーシップの関与が欠かせません。単なるITツールの導入だけでなく、企業のビジョンや目標と結びつけ、全従業員が知識の共有に参加する意義を理解することが、長期的な成功の鍵となります。
7.1. 暗黙知を形式知化するプロセスの全体像
暗黙知を形式知へ変換するうえで、まずは対象となるスキルや知識をどのように収集するかが重要です。
次に、その情報を整理し、どのような形式で共有するかを決定し、それらを共有・利用する段階では、全社員がアクセスしやすい仕組みと文化を育む必要があります。
最後に、実際の活用事例やフィードバックを集めることで、知識の精度や汎用性を高めることが理想です。
7.2. ナレッジ・リーダーシップによる知識ビジョンの策定
組織単位で暗黙知を形式知に転換するには、リーダーシップによる意思決定と具体的な指針が不可欠です。ナレッジ・リーダーシップとは、知識を企業の重要な資産とみなし、その活用に向けたビジョンと戦略を提示する取り組みを指します。これにより、従業員は暗黙知の共有やマニュアル作成に積極的になり、組織全体で一体感を持ってナレッジマネジメントを遂行できるようになります。
8. SECIモデルを活用した暗黙知の形式知化
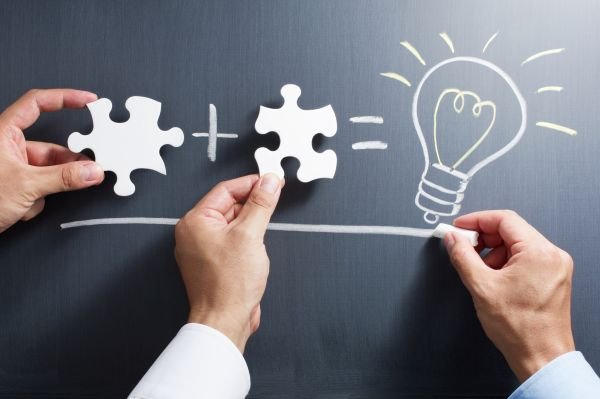
野中郁次郎氏が提唱するSECIモデルを用いることで、組織的に知識を循環・創造することができます。
SECIモデルはSocialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)の頭文字を取ったもので、知識がどのように生まれ、組織や個人の中で広がっていくかを示す枠組みです。
特に、暗黙知の形式知化に重要な役割を果たすのが表出化と連結化のステップであり、共同化と内面化がその前後を支える構造になっています。この循環プロセスが機能すれば、各メンバーが持つユニークな知見やアイデアが組織全体に広まり、さらに、そこから新たな発見が生まれるイノベーションの好循環が期待できます。
製造業の現場では、実際に手を動かしながらリアルタイムで学びを得るケースが多いため、このモデルの活用は取り入れやすい側面があるでしょう。SECIモデルを深く理解し、具体的なステップを社内で実践することで、暗黙知を体系的に可視化・共有できる可能性が高まります。特に、共同化を促進する場や表出化した情報をまとめる仕組みなどをデザインし、継続的に運用する取り組みが効果を生むでしょう。
ステップ1:共同化(Socialization)でノウハウを共有
共同化の段階では、言葉で表現しづらいノウハウを対面や現場の見学を通じて伝えることが中心です。たとえば、新人がベテランの作業を実際に観察し、一緒に作業することで感覚的に学ぶ手法があります。製造業では、現物を見ながらの説明に大きなメリットがあるため、研修やOJTはこの共同化フェーズの重要な場となります。
ステップ2:表出化(Externalization)で知識を言語化する
次に、暗黙知を言葉や図解、動画などで明確に示すプロセスが表出化です。ここでは、暗黙知を形式知に変換するために、作業手順をマニュアル化したり、インタビュー動画を撮影して共有したりします。言語やビジュアルといった多様な表現手段を使うことで、暗黙知の個人差を最小限に抑えながら共有できます。
ステップ3:連結化(Combination)で情報を整理・統合
表出化された個々の形式知を、組織全体で体系的にまとめるのが連結化のステップです。例えば、製造プロセスの全体フローに暗黙知が組み込まれた新しいマニュアルやデータベースを作成することで、多様な情報を一括管理できるようになります。連結化を適切に行えば、知識の重複や抜け漏れを防ぎ、活用しやすい形で情報を蓄積できます。
ステップ4:内面化(Internalization)で組織知を個人が活用
第四のステップである内面化は、組織に蓄積された知識を個々のスキルとして再度取り込むプロセスです。マニュアルや動画で得た情報を現場で活用することで、徐々に個人の暗黙知として蓄積されていきます。こうして一度形式知化された情報が、再び各人の行動指針や判断力として活かされるのです。
SECIモデルを促進する4つの「場(ba)」のデザイン
SECIモデルが機能するためには、共同化、表出化、連結化、内面化をサポートする「場(ba)」を設計することが重要です。例えば、実際に手を動かして学べる作業場、意見を交わすための会議室やオンラインチャット、ドキュメントを整理・編集するためのシステム環境など、多様なコミュニケーションの場が必要です。これらの場を整備し、有機的に結びつけることで、知識の創造と共有がスムーズに進みます。
9. ナレッジマネジメントツールの活用ポイント

知識共有をスムーズに進めるためには、ITツールの活用方法も理解しておく必要があります。
ナレッジマネジメントを支えるツールとしては、ドキュメント管理システムや社内SNS、ビデオ会議システムなどが代表的です。これらのツールを利用することで、リアルタイムに情報交換を行い、最新の知識を組織全体で共有することが容易になります。
製造業では文章だけでなく、動画や画像を用いたマニュアル作成も効果的です。実際の作業風景を撮影しておくことで、書面では伝えきれない細かなタイミングや手つきなどがわかりやすくなります。また、検索機能が充実しているツールを活用すれば、必要な情報をすぐに見つけられるため、生産現場のスピード感を維持できます。
一方で、ツールを導入するだけでは不十分であり、運用ルールの整備や利用促進の施策が重要です。定期的な勉強会やマニュアルの更新を行い、全員がツールを使いこなせるようにすることで、暗黙知の形式知化がより一層スピードアップします。
9.1.ドキュメント管理と動画・SNSによる知識共有
ドキュメント管理システムは、マニュアルや技術資料を時系列で管理し、更新履歴を追跡することができます。製造工程などを順次記録することで、トラブルシューティングが発生した際に過去の事例を参照しやすくなり、同じ課題を繰り返すのを避けることができます。社内SNSやチャットツールでは、リアルタイムでのやり取りが可能であるため、現場から直接フィードバックを受けながら、知識を高めることができるメリットがあります。
9.2. AIやクラウド活用で形式知化を効率化
AIを活用したデータ解析により、膨大な作業ログやセンサー情報から知見を抽出することが可能になります。さらに、クラウド環境を利用することで、遠隔地からでも最新のマニュアルや手順書にアクセスでき、現場と本部、さらには海外拠点との連携も強化されるでしょう。これらの技術を取り入れることで、情報検索や更新作業の効率を高め、形式知の作成・共有を迅速に行うことができます。
10. 製造業での属人化防止と生産性向上事例

具体的な企業や工場での成功事例を参照しながら、属人化を解消し生産性を向上させるポイントを見ていきます。
ある中堅製造企業では、熟練者による工作機械のセッティング手順を動画で撮影し、社内ポータルに掲載する取り組みを始めました。その結果、新人でも一定の品質で作業できるようになり、トラブルの大幅な減少に繋がったといいます。
別の例として、海外拠点を持つ大手企業が行ったのは、クラウドベースのナレッジ管理システムの導入でした。言語の壁を超えて動画や写真、翻訳テキストを共有し、新製品の立ち上げ期間を短縮することに成功しています。
このように、実際にツールを活用して暗黙知を見える化すると、時間や場所の制約を超えてスキルを伝えることができるようになります。属人化を解消するだけでなく、迅速なイノベーションにもつながるため、多くの製造企業が取り組みを進めているのです。
11. 暗黙知・形式知化におけるFAQと対策

暗黙知を形式知化する際には、よくある疑問や課題についての対処方法を整理します。
暗黙知の形式知化を進める際に、どの情報まで共有すべきか、整理の優先度をどのように決定するかなど、さまざまな疑問が生じます。また、高度に専門化した知識ほど、どのように言語化するかに悩む場面も多いでしょう。
これらの課題を克服するためには、知識の機密レベルや社外提供の可否を整理しながら進めることが重要です。特にコア技術に関しては、知識共有と情報漏えいのバランスを取るための厳格なルール設定が求められます。
さらに、組織全体で知識の共有をよりオープンにすることで、従業員の参画意識が高まります。FAQやガイドラインの整備はもちろん、定期的なワークショップや勉強会を開催して、相互学習の機会を増やすことも効果的です。
11.1. 知識の保護と権限設定の重要性
機密性の高い情報は、誰もが見られる状態になるとリスクが大きいため、アクセス権限を細かく設定したり、重要な情報は暗号化したりするなどの対策が必要です。特に、海外と取引がある企業や特許技術を持つ製造業では、情報が外部に流出しないように内部統制を強化し、適切なメンバーにのみ知識が共有される仕組みを構築することが重要です。
11.2. 高難度スキルへのアプローチと継承方法
高度な職人技や長期間の経験によって培われるスキルは、簡単に言語化することが難しいものです。しかし、動画やセンサーなどのテクノロジーを活用して動作解析を行い、作業の微妙な差異を記録することは可能です。また、若手と熟練者をペアリングさせるメンター制度の導入によって、実際の作業を通じて技術を継承する仕組みを構築することも有効な方法でしょう。
12. まとめ

暗黙知の形式知化は、企業活動を円滑に進め、競争力を高めるために非常に重要なプロセスです。
暗黙知は職人の勘や豊富な経験に裏打ちされた貴重な知識であり、形式知は誰もが共有しやすい客観的な情報です。両者を適切に活用することで、製造業の技術伝承が進むとともに、さらなるイノベーションも期待できます。SECIモデルやナレッジマネジメントの手法を用いて、暗黙知を体系的に可視化することが重要です。とりわけ、情報共有の仕組み作りやツール導入の際には、企業独自の文化や技術領域に応じた最適化が必要です。
最終的には、従業員全員が知識創造に参加できる環境を整備することで、属人化を防ぎつつ競争力を高めることができるでしょう。暗黙知と形式知をうまく融合させ、今後の変化の激しい時代を乗り越える基盤を早めに構築しましょう。