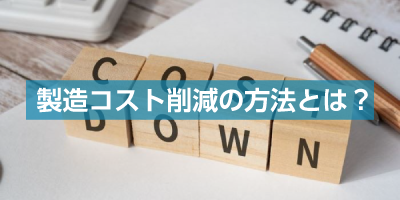BOMとは? ものづくりとITをつなぐ部品表の全体像
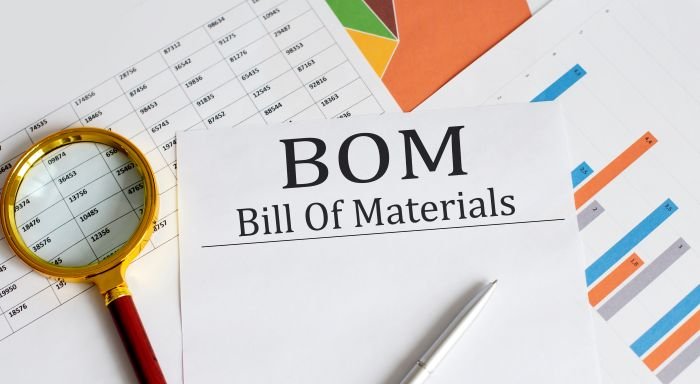
BOM(Bill of Materials)は、製品を製造するうえで必要な部品や資材の情報を整理・統合した部品表です。ものづくりの効率化に欠かせない要素であり、ITを活用した情報管理の中心的な役割を担います。
本記事では、BOMの定義や種類、構成要素の管理手法からシステム連携までを包括的に解説し、今後の動向と展望についても考察します。
目次
1.2. ビジネス・製品ライフサイクルにおけるBOMの重要性 2.1. EBOM(エンジニアリングBOM)とは
2.2. MBOM(マニュファクチャリングBOM)とは
2.3. SBOM(ソフトウェアBOM/サービスBOM)の特徴
2.4. その他(P-BOMや複合BOMなど)の位置づけ 3.1. 部品番号・部品名と階層構造
3.2. 数量・代替部品・オプション構成の管理
3.3. リビジョン(版数)と品目管理の重要性 4.1. 部品情報の収集・整理と階層設計
4.2. サマリー型とストラクチャー型の違い
4.3. 運用フローの設計と継続的改善 5.1. コスト管理・在庫管理・変更管理への効果
5.2. システム連携(SAPなど)と品目コード整備 6.1. CSVやExcelでの運用時の注意点
6.2. ERP・生産管理システムとのデータ連携 8.1. サプライチェーンDXとBOM統合管理
8.2. IoT・クラウド活用によるBOM運用の進化
1. BOM(部品表)の定義と役割

まずはBOMの基本的な考え方と、それが果たす役割を明らかにします。
BOMは、製品を構成するあらゆる部品や材料をリスト化して体系的に管理する仕組みです。この仕組みにより、設計段階から製造、調達、販売、アフターサービスまでの情報が共有され、部門間のコミュニケーションギャップを低減できます。紙やExcelなどで複数箇所に分散されていた情報を一元化することで、人為的なミスも大幅に減らせる点が大きな特徴です。
また、部品構成を明確に可視化することで、製品展開時の改良や新仕様追加などの変更管理が容易になります。BOMを通じて必要な情報を速やかに共有できるため、調達リードタイムの短縮や在庫の最適化も期待できるでしょう。このような総合的な管理が、ものづくり全体の生産性向上と品質維持に寄与します。
1.1. BOMが果たす役割とメリット
BOMは、単なる部品のリストではなく、製品に関する情報を横断的に結びつける重要なインフラです。たとえば、設計部門が作成したデータを製造部門が参照することで、部品不足や適合性の問題を早期に発見することができます。さらに、購買部門がBOMを基にしてコスト管理を行うことで、適切なサプライヤーの選定や部品調達が進むというメリットもあります。部門間コミュニケーションの効率化に加えて、作業の重複を防ぐことにも大きな効果があると言えるでしょう。
1.2. ビジネス・製品ライフサイクルにおけるBOMの重要性
製品はアイデア段階から設計・製造・販売・保守・廃棄に至るまで、さまざまな工程を経てそのライフサイクルを全うします。この全工程をつなぐ基盤となるのがBOMであり、正確な部品情報や構造情報がなければ、適切なコスト試算や生産計画を立てることは難しくなります。さらに近年では、リサイクルや環境対応の観点からも部品追跡が必要とされており、BOMの情報を参照源として活用するケースが増えています。
2. BOMの種類:EBOM・MBOM・SBOMなど

BOMには複数の種類があり、用途や業務プロセスに応じて使い分けられます。"BOM"と一口にいっても、設計フェーズや製造フェーズ、保守フェーズなどで異なる形式が用意されています。部門ごとに別々の情報を保持してしまうと、後工程で矛盾が生じるリスクが高まるため、各BOMを整合性のある形で管理することが重要です。
また、BOMの見た目や構成も異なり、大まかに部品をリストアップするサマリー型や、親子関係を階層で示すストラクチャー型などがあります。どの形式を用いるかは、業務の規模や製品特性によりますが、複数のBOMをどのように連携させるかも大きなポイントとなります。
2.1. EBOM(エンジニアリングBOM)とは
EBOMは、設計部門が中心となって管理するBOMです。主に製品の設計データを反映するため、CADやCAEなどで作成された図面や仕様書との整合性が重要になります。新しいモデルや改良版を開発する際には、EBOMを更新し、その情報が以降のフェーズで適切に流用されるかどうかが、開発効率や品質に大きく関わってきます。
2.2. MBOM(マニュファクチャリングBOM)とは
MBOMは、製造工程で使用されるBOMとして位置づけられます。設計上の部品情報を製造現場の作業視点で再構成することが特徴です。新しい製品を生産する際のラインの効率化や、改良・新仕様追加の際の迅速な変更管理において、MBOMが重要な役割を果たします。さらに、部品を効率よく組み合わせることで、製造コストを削減し、在庫管理の最適化も期待されます。
2.3. SBOM(ソフトウェアBOM/サービスBOM)の特徴
ソフトウェア製品や、製品に付随するサービスを対象としたBOMがSBOMです。近年、物理的な部品だけでなく、ファームウェアやアプリケーションソフトのバージョン管理、省略できないライセンス情報なども扱うケースが増えています。特に製造業ではSBOMの整備が極めて重要となっています。
2.4. その他(P-BOMや複合BOMなど)の位置づけ
購買部門が重視するコストや部品調達先の情報をまとめたP-BOM(購買部品表)や、複数の部門情報を統合する複合BOMも存在します。たとえば、組立ラインごとに生産内容が異なる場合、複合BOMを用いることで、調達スケジュールと製造スケジュールの整合をとりやすくなります。BOMの多様化は、企業の生産形態やビジネスモデルに合わせて最適化されるのが一般的です。
3. BOMを構成する要素とデータ構造

BOMを扱う際には、部品番号や階層構造などの必要な情報項目とその管理方法を理解することが重要です。
BOMはシンプルに見えますが、実際は多数のデータ項目が重層的に関連しています。部品番号はもちろん、用途、サイズ、材質、数量など、複数の属性を組み合わせて製品情報を整理します。正確なデータ構造を構築できれば、情報の取り出しや分析が容易になり、変更管理やコスト算出もスムーズに行えるでしょう。
しかし、構成が複雑になると、データの更新漏れや冗長化のリスクが高まります。バージョン管理をしっかり行い、誰がどのタイミングで情報を変更したのかを追跡できる仕組みを整えることが、BOMを長期的に活用する上で欠かせません。
3.1. 部品番号・部品名と階層構造
部品番号や部品名の設計は、BOMをわかりやすく保つための第一歩です。たとえば、コード体系を製品カテゴリや機能単位で分ければ、製品全体の階層構造を把握しやすくなります。階層を管理することで、一つの部品がどの製品のどの部分に使われているかを素早く追跡することが可能です。
3.2. 数量・代替部品・オプション構成の管理
BOM上で数量をしっかりと管理することは、在庫不足や過剰在庫を防ぐために重要です。BOMは単に設計データの集まりではなく、継続的な更新が求められます。例えば、新しいモデルや改良版を開発する際にはEBOM(設計部品表)を更新し、以降のフェーズでその情報が適切に流用されることが求められます。
さらに、近年のリサイクルや環境対応の課題もあり、部品追跡の重要性が増しています。代替部品やオプションをあらかじめBOMに登録しておくと、緊急時の対応や柔軟な生産計画が容易になるメリットがあります。複数のBOMを効果的に連携させることが、業務の効率向上や製品特性に応じた最適化にも関わるため、重要なポイントとなります。
3.3. リビジョン(版数)と品目管理の重要性
製品がアップデートされる際には、リビジョン(版数)の管理が欠かせません。BOMの各構成要素がいつ、なぜ変更されたのかを記録することで、過去の状態に迅速に戻せるため、トラブルシューティングに役立ちます。さらに、リビジョン履歴と品目管理を結びつけることで、同じ部品でも異なるバージョンが混在する状況を正確に把握できるようになります。
4. BOMの作成・管理ステップ

実際にBOM(部品表)を作成・運用するための基本的な流れを紹介します。
BOMの作成には、まず部品情報を収集し、適切な階層構造を整えるプロセスがあります。その上で、サマリー型かストラクチャー型かを選び、運用上のフローを定義するのが一般的です。その後、変更要求への対応や継続的なメンテナンスが必要であるため、最初の構成設計でいかに柔軟性を持たせるかが重要です。
また、作成・管理の各ステップにおいて、関係部門との情報共有を早い段階で行うことが重要です。変更があった際に迅速に反映できる体制があれば、リリースまでのリードタイムも短縮できるでしょう。
4.1. 部品情報の収集・整理と階層設計
BOM構築の初期段階では、どの部品が必要なのか、どのような属性を持つのかといった情報を広く収集します。その後、類似部品のカテゴリ分けや階層構造の決定を行い、必要に応じて部品番号の割り振り方針を策定します。これらをしっかりと整理することで、後の運用の混乱を避け、変更管理も視覚的に把握しやすくなります。
4.2. サマリー型とストラクチャー型の違い
サマリー型BOMは、すべての部品を平面的に一覧化する方法で、全体像をつかみやすい利点があります。一方、ストラクチャー型は親子関係を階層で示すため、組み立て工程を意識しやすく、特定の部品がどのユニットに属するのかを瞬時に把握できます。どちらを選ぶかは、製品の複雑度や社内での使いやすさを考慮して決めることが多いです。
4.3. 運用フローの設計と継続的改善
BOM作成後は、日々の変更や追加に対応する運用フローを設計する必要があります。たとえば、新しい部品が適用されたときにどの部署が承認するのか、新リビジョンをいつ反映するのかなど、明確な手順を定義することで混乱を防ぎます。さらに、定期的に運用状況をレビューし、新たな課題や改善点を洗い出し、継続的にシステムや運用ルールを更新していくことが不可欠です。
5. BOM管理システム導入のメリットと課題

BOMを効率的に管理するためには、専用システムの導入が効果的ですが、それに伴って克服すべき課題もあります。
BOM管理システムを導入すると、情報の一元化と権限管理が可能になり、各部署が最新のデータに容易にアクセスできるようになります。変更の履歴と承認フローも自動化され、作業効率の向上とミスの低減が期待できます。しかし、システム導入には初期コストや教育コストが発生し、既存システムとの連携が課題になることを予測して計画を立てる必要があります。
システム化によって調達コストが削減され、在庫管理や変更管理が迅速化するなど、多くの利点が得られます。さらに、ERPや生産管理システムと連携することで、財務や販売、物流の情報をシームレスにつなげることが可能です。これらの連携により経営判断の精度も向上し、包括的な業務の最適化が期待できます。
5.1. コスト管理・在庫管理・変更管理への効果
BOM管理システムにより、必要な部品数や調達費用を正確に把握でき、無駄な在庫を抱えずに済む効果があります。また、変更管理の手続きをワークフロー化することで、担当者ごとの作業状況や進捗を可視化でき、製品アップデートに伴う混乱も最小限に抑えられます。その結果、コストダウンとスピードアップの両立が実現します。
5.2. システム連携(SAPなど)と品目コード整備
ERPやSAPなどの基幹システムとBOMを連携させる際は、品目コードの設計を統一しておくことが重要です。異なるシステムで同じ部品が異なるコードを持つと、データの突合や在庫管理経路で混乱が生じる恐れがあります。システムを連携させる際には、データの統一性を確保するために、コードを整合させる必要があります。
6. BOMとIT:CSVファイルやクラウドERPとの連携

手軽な管理方法から高度なシステム連携まで、BOMとITの関わり方は多様です。
小規模な企業や導入初期では、ExcelやCSVファイルを使ってBOMを管理することもよくあります。
一方、大規模プロジェクトやグローバル展開を視野に入れる場合、クラウドERPと連携してリアルタイムに情報を更新する仕組みが求められます。どの程度のスピード感や正確性が必要なのかを検討し、自社に合った連携方式を選ぶことが重要です。
クラウドサービスを活用すれば、遠隔地の工場やサプライヤーとも一貫したデータを共有でき、拠点間で情報の差異が生じにくくなります。特に、複数国に生産拠点がある企業や、テレワークが多い企業では、クラウドERPを活用したBOM連携の恩恵が大きいです。
6.1. CSVやExcelでの運用時の注意点
スプレッドシートを使用したBOM管理は、導入コストが低く、手軽に始められる点が魅力です。しかし、複数人で同時に編集するとデータの整合性が乱れやすく、変更履歴の管理も難しいという弱点があります。定期的にバックアップを取り、シートのバージョン管理を行うなど、運用ルールを明確にすることで、リスクを軽減できます。
6.2. ERP・生産管理システムとのデータ連携
BOMをERPや生産管理システムと連携させると、在庫状況や受注情報といったリアルタイムの数値データが即時に反映され、経営判断を迅速に行えるようになります。たとえば、需要予測の精度向上や生産計画の即時変更にも柔軟に対応できるなど、スピード感のあるものづくりを実践する上で大きな武器となるでしょう。
7. GrowOne 生産SRでBOM管理

具体例として、GrowOne 生産SRにおけるBOM管理機能や活用メリットを紹介します。
GrowOne 生産SRは、生産管理に必要な多機能を搭載したシステムで、BOM管理機能もその中核を担います。部品表の作成や階層管理、リビジョン管理などが一元的に行え、設計部門・製造部門・保守部門がスムーズ情報共有できる点が特徴です。連携機能も充実しており、他のPDMシステムやCADソフトとデータ連携し、設計情報を一から再入力することなく、製造部門に連携することも可能です。
また、現場の運用を意識した設計になっているため、ユーザーフレンドリーな画面構成や柔軟なカスタマイズが可能です。自社の業務プロセスに合わせて機能拡張を行いながら、段階的にBOM管理を高度化していくこともできるため、これからデジタル化を進めたい企業にとって有力な選択肢と言えるでしょう。
8. 今後のBOM管理の動向と将来展望

AIの活用やサプライチェーンDX(デジタルトランスフォーメーション)の潮流を踏まえ、BOM管理の未来を展望します。製造業全体がデジタルトランスフォーメーションに向かう中で、BOM管理にも大きな変革の可能性が見込まれます。
特に、AIを活用した部品選定や需要予測の進展により、より柔軟で自動化されたBOM更新が期待されます。また、サプライチェーン全体での部品情報の入力・共有の自動化など、次世代の運用方法が普及していくでしょう。
今後は、環境対応やリサイクル関連の情報もBOMに含め、包括的なライフサイクル管理を実現する動きが加速すると考えられます。製品ごとのカーボンフットプリントを管理するなど、より詳細な情報の透明性が求められる中で、BOMは単なる部品表を超えた戦略的ツールとしての役割を果たしていくでしょう。
8.1. サプライチェーンDXとBOM統合管理
サプライヤーや外注先とのやり取りをデジタル化する動きがさらに進行しており、BOMを活用することでサプライチェーン全体での部品在庫や生産計画を調整する重要性が増しています。これにより、余剰在庫や納期遅延を最小限に抑えられます。また、サプライチェーン全体における部品追跡の容易化により、不具合が発生した際の原因究明や対応スピードが飛躍的に向上するでしょう。
8.2. IoT・クラウド活用によるBOM運用の進
センサーやIoTデバイスから収集されるリアルタイムデータをBOMに反映し、稼働状況や品質情報を即座に更新する取り組みが進んでいます。クラウドサービスを活用することで、各拠点や外部パートナーが同一のBOMデータを参照し、その場で更新内容を共有することが可能です。これにより、生産状況の変化に合わせたタイムリーな対応が可能となり、全体の最適化を図りやすくなります。
9. まとめ・総括

最後に本記事のポイントを振り返り、BOM(部品表)管理の重要性と今後の取り組みについて簡潔にまとめます。
BOMは製造業において、効率的な設計・製造・調達を支える基盤となっており、部門間の連携、コスト削減、品質向上に大きく寄与しています。EBOM(設計部品表)やMBOM(製造部品表)など役割に応じた多様な形態があり、システム化による管理の高度化により、グローバル規模での情報共有やサプライチェーン全体の最適化が可能になります。
今後はAIやIoTなどの技術革新と組み合わせることで、さらに自動化が進み、リアルタイムでの管理が実現されることが期待されます。